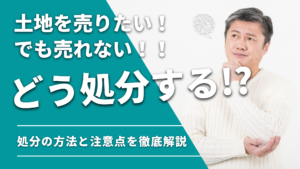「土地活用に興味があるけど、右も左もわからない」
「使っていない土地があるが、最適な活用方法がわからない」
こういったお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ビジネスとして土地を活用したいけど、方法がわからないといった方に向けておすすめの土地活用について紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
土地活用でビジネスは可能?
まずは土地を活用してビジネスができるのか、土地活用とはどういうものなのかなど、土地活用の基礎知識について解説します。
土地活用でのビジネスは可能

結論からお伝えすると、土地活用でのビジネスは可能です。土地を所有していながら有効活用せずに放置しておくのは、むしろ機会損失といえるでしょう。
なぜなら、その土地を活用して得られるはずの収益を取りこぼしている可能性があるからです。
土地は所有しているだけで税金や公共料金などの維持費がかかります。
厳密には土地の状況によって異なりますが、固定資産税や都市計画税の支払いは毎年必要であり、建物に電気や水道が通っているなら、基本料金も発生するでしょう。
活用しなければ出費がかさむばかりですので、何らかのビジネスによって維持費をまかなう必要があります。
土地活用には5つの方法がある
土地活用は、大まかに分けると5つの方法があります。
- 建物を建てて賃貸に出す
- 建物を建てて運営する
- 土地を貸す
- 駐車場などの方法で暫定利用する
- 売却・交換する
以上の5つについて詳しく解説します。
建物を建てて賃貸に出す
1つ目は土地に建物を建てて、賃貸に出す方法です。
例えば、老人ホームを建てて、他の事業者に建物を丸ごと貸し出すといった方法が考えられます。
その他、ロードサイドの土地であれば、コンビニ用の建物を建てて貸し出すことも可能です。
ただし、建物を建てるためには相応の初期投資が必要であるため、投資分を回収して利益を出せるように、土地の特徴や条件に適した活用方法を選ぶことが肝要です。
建物を建てて運営する
建物を建てて運営する方法もあります。例えば、老人ホームやコンビニエンスストアを建てた場合、第三者に貸し出さずにオーナー自身が運営するなどです。
その他、賃貸アパートや賃貸マンションを建てたり、コインランドリー用の施設を建てたりといった方法が考えられます。
自分で運営する分収益性は高くなりますが、労力がかかる点、経営状況によっては赤字になる可能性がある点には注意しなければなりません。
土地を貸す
土地を活用したい人に土地を貸す方法です。
借り主が駐車場として活用したり、アパートやマンション、老人ホームやコンビニエンスストアを建てて事業運営をしたりなどの活用が考えられます。
土地貸しは、オーナー自身が初期費用を負担する必要がほぼないため、ローリスクで始められます。しかし、収益源が「建物の賃料」ではなく「土地の地代」となるため、基本的に大きな収益を狙うことが難しいです。
駐車場などの方法で暫定利用する
駐車場などの方法で暫定利用する方法もあります。
現時点で活用方法が定まっていない場合、駐車場として活用するのであれば、そこまで初期費用をかけずに活用を始められます。
将来的に賃貸住宅を建てる場合も、駐車場であれば撤去費用の負担が小さく、用途変更をしやすいです。
活用方法が決まらないからと言って土地を放置しておくと、収益がない状態で固定資産税が発生したり、管理の手間が発生したりします。
「将来的には活用したいけど、今は維持費を補填する程度に活用しておきたい」といった方にオススメです。
売却・買い替え
自分で土地活用をしない場合や第三者への貸し出しも考えていない場合は、売却・交換するのも手です。
売却できればまとまった現金が手に入るだけでなく、土地を管理する必要がなくなり、固定資産税などの維持費の支払いからも解放されます。
買い替えは、土地を売却して別の不動産を取得することです。取得したい不動産がある場合は買い替えを検討してみましょう。
土地活用のメリット・デメリット

こちらでは土地活用のメリットとデメリットをそれぞれ解説します。
メリット
土地活用をおこなうメリットは、
- 安定した収入
- 節税効果
- 建物の老朽化の抑制
の3つです。以下で詳しく解説します。
安定した収入
どのような活用方法を選ぶにしても、事業を始めて利益を出すという構造は同じです。そのため、事業が安定すれば、長期にわたって安定した収入を得られる可能性があります。
節税効果
節税対策と相性が良いのも土地活用の特徴の1つです。
例えば、空き地に賃貸住宅用の建物を建てた場合、要件を満たせばその土地は「小規模住宅用地」としてみなされます。
小規模住宅用地は特例として固定資産税の軽減措置が適用されるため、面積が200㎡以下の土地に関しては、建物がない状態と比べて課税額が6分の1になるのです。
他にも所得税や住民税、相続税、都市計画税など、活用方法によって様々な節税効果を期待できます。
建物の老朽化の抑制
長期的に土地活用をおこなうにあたり、建物の修繕や設備のメンテナンスを正しくおこなうことで、老朽化の抑制につながります。
デメリット
デメリットはどのような活用方法を選ぶかによって異なります。
- 初期費用がかかる
- 金利の支払いが発生する
- 空室リスクを抱える
- 税金の軽減措置が適用外となることがある
- 用途変更がしにくくなる
こちらでは以上の5つのデメリットを解説します。
初期費用がかかる
アパート・マンションやビル、商用施設などを建設する場合、およそ数千万円〜数億円の初期費用がかかります。
コインパーキングやトレーラーハウスを経営する場合でも、専用機器の設置やコンテナのレンタル・購入などの初期費用が数百万円はかかるでしょう。
金融機関のローンを利用すれば初期の負担を減らすこともできますが、毎月の返済義務が発生します。
金利の支払いが発生する
金融機関のローンを利用すれば金利が発生するため、長期にわたって元金と利息を支払い続けることになります。
空室リスクを抱える
ローンを活用してオーナー負担で建物を建てた場合、オーナーには毎月金融機関への返済義務が発生します。しかし、空室があれば返済の当てである家賃収入が減るため、資金繰りに苦労するでしょう。
税金の軽減措置が適用外となることがある
住宅用地であれば、固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されます。しかし、オフィスビルの経営・駐車場や工場・倉庫などは住宅用地ではないため、同様の軽減措置を受けられません。
用途変更がしにくくなる
更地、工場、倉庫、駐車場などの場合は、建物の解体や土地の整備をするハードルが低く、途中で土地の用途変更をしやすいです。
しかし、賃貸アパート・マンションやオフィスビル、商用施設などの場合は容易に用途変更ができません。
建物を再利用するのであれば、改修費用のみになりますが、解体して新しい活用を始める場合は大規模な解体工事が必要です。規模によっては数千万円〜数億円単位の解体費用が発生するでしょう。
さらに、賃貸住宅経営では、賃貸借契約の内容が「更新制」であることが一般的です。
入居者が解約を申し出ない限り、原則としてオーナーは部屋を貸し続ける義務がある点にも注意が必要です。
一方で商用施設の場合は、更新制がない代わりに、数年から十数年といった長期間で賃貸契約を結ぶことが珍しくありません。契約期間中に用途を大きく変更するのは容易ではないでしょう。
管理業務が発生する
基本的にどのビジネスモデルにも言えることですが、土地活用をする以上、土地や建物の管理業務が発生します。
専門業者に管理を委託することもできますが、固定費が発生するため、年間の利回りは下がってしまいます。
このように、土地活用にはデメリットやリスクが数多くあります。これらのリスクの回避方法について知りたい方は以下の記事を参考にして下さい。

土地活用のビジネスモデルで収益化しやすい活用方法3選

土地活用のビジネスモデルは数多くありますが、こちらでは王道の活用方法を3つ紹介します。
賃貸住宅経営
賃貸住宅経営は、賃貸アパート・マンション、賃貸併用住宅などを建てて、入居者から賃料を得るビジネスモデルです。
入居者がいる限り、安定した収益を実現しやすいと言えます。
また、アパート・マンションは住宅用地なので、税制面でもメリットも大きいです。
建物がない更地と比較すると、住宅用地は固定資産税が6分の1まで軽減され、都市計画税は3分の1まで軽減されます。
さらに、「相続税」の節税効果も期待できます。
更地の状態と比べて住宅用地は、所有者自身の土地の利用が制限されているという観点から、相続税が15%~20%ほど軽減されるのです。
このように、収益面や税制面でメリットが多い住宅の賃貸経営ですが、いざ始めるとなると、それなりに初期費用がかかります。
金融機関から融資を受ければ初期費用を抑えられますが、その分金利がつくので、最終的な出費の合計額は増えます。
空室が発生するリスクもあるため、修繕費やリフォーム費用、広告費などの想定外の出費により、収支のシミュレーションが崩れてしまうこともあるでしょう。
また、入居者による家賃の滞納、住民間のトラブルも住宅の賃貸経営では珍しくありません。
オーナー自身がそれらの問題に対応するのが困難な場合、管理会社に管理業務を委託できますが、月々のコストは増えます。
以上のことから、手元にしっかり利益を残すためには、いつどこでどのようなコストが発生する可能性があるのか、事前に把握した上で事業計画を立てる必要があります。
さらに、賃貸アパート・マンションは競合が多いのも悩みどころです。家賃設定、立地、デザイン性、機能性、間取り、駐車場の有無など、各々の強みを生かして、しのぎを削りあっています。
また、地域の特性によって、求められる住居のタイプが異なる点にも注意が必要です。
例えば、学生の多い地域、ファミリーが多い地域、単身赴任の会社員が多い地域など、年齢層や世帯の違いによって求める住居のタイプは異なるでしょう。
このように、高い入居率を実現して安定した利益を出すためには、事前に市場のニーズを把握しておく必要があります。
土地活用の賃貸経営については、こちらも併せて参考にして下さい。
-300x170.png)
駐車場経営
駐車場経営には、大きく分けて「月極駐車場」と「コインパーキング」とがあります。
月極駐車場の主なメリットは、初期費用が抑えられる点です。
土地の状態が悪ければコストを割いて整備する必要がありますが、そうでない限り、土地さえあればすぐにでも始められます。
デメリットは、税制面での優遇措置がない点です。
例えば、住宅用地のように固定資産税が大幅に軽減されることはありません。そのため、税金の支払いが負担となり、駐車場経営をやめて土地を売却する人もいます。
また、月極の場合は使われずに空いているスペースはデッドスペースになるのもデメリットです。1件でも多くの契約を取り、空きスペースを減らすのが利益を最大化するポイントと言えます。
それに対して、コインパーキングは時間貸しのため、「回転率」を重視した戦略がとれます。飲食店と同様で、利用客が時間帯によって入れ替わるため、回転率が高まるほど利益が増えていきます。
専用機器のレンタルや設置費用、管理会社への委託費用など、月極駐車場と比べて出費は増えますが、その分大きな利益を狙えるビジネスモデルと言えるでしょう。
立地としては、大型の駐車場が備わっていない小中規模のビル・飲食店の近隣など、いかに車移動している人のニーズを満たせるかが重要です。
コインパーキング経営を成功させるためには、
・湿度や温度の調整といった環境面での配慮がされていること
・セキュリティ面で荷物の安全が確保されていること
・適切な賃料設定であること
これらに配慮することがポイントと言えるでしょう。
賃貸併用住宅経営
賃貸併用住宅とは、オーナーが住む住宅と賃貸として第三者に貸し出す住宅が混在する建物のことです。1階を自宅に、2階を賃貸住宅にするケースが一般的です。
賃貸併用住宅のメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。
まずメリットですが、1つ目はローン返済の負担を軽減できる点です。
毎月の家賃収入をローン返済に充てられるため、経済的なメリットが大きいと言えます。
また、住宅ローンを活用できる点もメリットです。通常、賃貸住宅を建てる際は不動産投資用のローンが適用されるため、住宅ローンを活用できません。
しかし、賃貸併用住宅は一定の要件(51%以上が自己居住用であるなど)を満たしていれば、住宅ローンを活用できます。
一般的に不動産投資用のローンよりも住宅ローンの方が金利が低く、返済期間も長いため、月々の返済負担がかなり軽減されます。
さらに、賃貸併用住宅は賃貸住宅でありながら住宅ローン控除を受けられる点もメリットです。借入開始から毎年10年間、年末に残高の1%を還付してもらうことができます。
例えば、年末の残高が3000万円であれば、1%分である30万円の還付を受けることが可能です。
月単位だと2万5千円の還付になるので、家賃収入と合算すると、ローンを返済して手残りがプラスになることさえあります。
3つ目のメリットは、居住用住宅と賃貸用住宅を別々に建てるより、一緒に建てた方がコストが浮く点です。
コストがかかりやすい基礎や屋根などが1棟分で済むため、初期費用を抑えやすいと言えます。
4つ目のメリットは、節税効果を期待できる点です。
例えば、マイホームに適用される固定資産税の軽減措置は、通常の賃貸住宅には適用されません。
しかし、賃貸併用住宅であればマイホームとして認められるため、軽減措置を受けられます。1戸につき200㎡までは固定資産税が6分の1に、200㎡を超える部分に関しては3分の1に軽減されるのです。
同様に、賃貸併用住宅は相続税においても節税効果を期待できます。
相続税の評価は、自宅より賃貸住宅の方が低い評価を受けるためです。さらに小規模宅地等の特例が適用されれば、最大330㎡の範囲まで80%の軽減を受けられます。
小規模宅地の特例に関する詳細は、国税庁のサイトを参照して下さい(※1)。
続いて、賃貸併用住宅のデメリットについて解説します。
1つ目のデメリットは、オーナー自身も住むため、収益を最大化できない点です。通常の賃貸住宅であれば、満室稼働を目指して収益を最大化しようとします。
しかし、賃貸併用住宅は主に1階部分にオーナーが住む必要があるため、最低でも1部屋分の賃料を得ることができません。
2つ目のデメリットは、入居者との距離が近い点です。
入居者を監視しやすいという点ではメリットですが、人によっては距離が近すぎて気を遣ってしまう可能性があるでしょう。
3つ目のデメリットは、売却に不利である点です。
賃貸併用住宅は、自己居住用としても収益物件としてもどちらつかずな側面があり、使い勝手が悪いと感じる買い手から敬遠される傾向があります。
将来的に売却を検討しているのであれば、買い手が好みそうな間取りや価格設定にしておく必要があるでしょう。
初期費用を抑えやすい活用方法8選
「土地活用に興味はあるけど、最初はできるだけ初期費用を抑えたい」という人もいるでしょう。
そこでこちらでは、初期費用を抑えやすい活用方法を8つ厳選して紹介します。メリット・デメリットも解説するので、併せて参考にして下さい。
テナント貸し
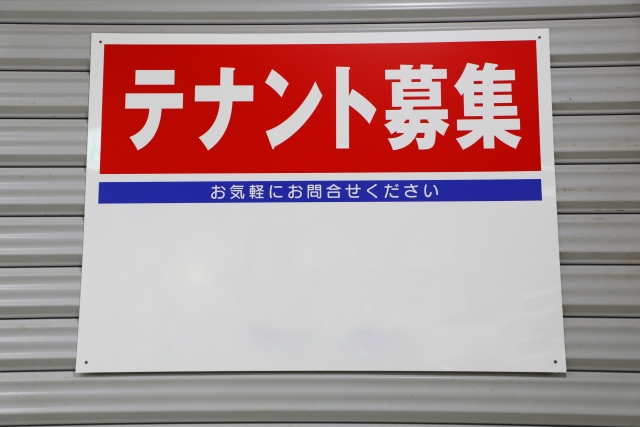
「テナント貸し」とは、一般的にオフィスビルや商業施設を建てて、そこにテナントを誘致し、賃料を得るビジネスモデルです。
ただし、テナント側との契約内容によっては、土地のみを貸し、建物の建築費用をテナント側が負担することもあります。その場合、オーナー側で建物を建てないため、初期費用の負担が大幅に軽減されます。元々相続した土地であれば、土地を貸すだけなので、初期投資はほぼゼロです。
テナント貸しのメリットとしては、住宅用と比べて賃料を高めに設定しやすい点です。テナント側の目的は、その場所を借りて事業をし利益を生むことなので、賃料以上の収益を生み出せる見込みがあれば、賃料が高くても入居しやすい傾向があります。
また、オフィスビルや商用施設では、アパート・マンションでありがちな入居者同士のトラブルも起きにくく、管理しやすいという点もメリットでしょう。一棟をまるごと貸し出す場合は、テナント側が建物を管理することも多く、オーナー側の負担がより軽減されます。
このように、一見メリットが多く思えるテナント貸しですが、利益を出せるかどうかは話が別です。
まず、前提としてテナントにとって魅力的な立地に、土地を所有している必要があります。その上で、テナントの仲介が得意な不動産会社に地道な営業活動をしたり、広告を使って宣伝したりといった施策が必要な時もあるでしょう。テナントが決まったあとには、賃料の交渉や経費区分の取り決めなどの神経質な作業も控えています。
基本的には長期に渡る契約がほとんどなので、十分に収支のシミュレーションをし、契約内容を吟味しましょう。契約が無事完了しても安心はできません。なぜなら、テナント側の事業が常に安泰とは限らないからです。
もし経営が傾いて賃料の支払いが滞れば、契約期間の満了前に退去する可能性もあります。テナント貸しならではのデメリットと言えるでしょう。
賃料が高いほど、空室になった時の損失は大きいです。そういった不測の事態によって経営が圧迫されないように、手元資金は常に余裕を持たせておく必要があります。土地活用でテナント貸しをするなら、以下の記事も併せてお読みください。

トランクルーム経営
トランクルーム経営は、荷物の保管場所を求めている人に対して、コンテナを貸し出して保管料金を得るビジネスモデルです。
厳密には、「自分自身でコンテナを購入して利用者に貸す方法」と、「トランクルーム経営をしたい業者に土地、建物、コンテナをまとめて貸す方法」とがあります。
オーナー自身がコンテナを購入する場合、9坪くらいのものが1台450万円前後であるため、規模で始める場合は初期投資を抑えやすいでしょう。後者を「一括借り上げ方式」と言い、実態は先述のテナント貸しと同様です。
この方法であれば、オーナー自身は管理業務をする必要がなく、基本的に業者がすべて運営することになります。売り上げの状況に関係なく、毎月安定した賃料を得られるので、オーナー自身が空室リスクにさらされる心配はありません。
安定して利益が出るのは大きなメリットですが、間に業者を挟む分、利益率は自身で運営するよりも下がってしまいます。また、税制面での優遇措置もとくにないので、リスクが小さい分リターンも小さめのビジネスモデルと言えます。
資材置き場
資材置き場とは、建築業者などが一時的に資材を保管しておくための場所です。空いている土地を資材置き場として貸し出すことで、初期費用をほとんどかけずに賃料を得られます。
資材置き場として活用する1つ目のメリットは、長期的に安定収入を得やすい点です。資材置き場の契約は一般的に長期に及ぶ傾向があり、数年単位で安定した収益を期待できます。
2つ目のメリットは、初期費用がほとんどかからない点です。
資材を置くスペースさえあれば問題ないため、土地を整形・舗装する必要がありません。そのため、他の活用方法と比べて初期費用を抑えやすい特徴があります。
3つ目のメリットは、転用しやすい点です。
定期借地ではないため、借地借家法の対象となりません。そのため、他の用途に転用する際もオーナー側の都合でスムーズに解約できます。ただし、その際は解約時に違約金が発生しないような契約内容にしておく必要があります。
4つ目のメリットは、不整形地や不便な立地でも活用できる点です。
資材置き場を運営する上で必要なのは、たくさんの資材を置ける十分な広さです。そのため、立地の良さや日当たり、土地の大きさや形は重要ではありません。
5つ目のメリットは、管理をする必要がなくなる点です。誰にも使われていない土地は草木が生え放題となったり、不法投棄や不法駐車の温床になったりすることがあります。
そのような状況を防ぐためにオーナーは定期的に土地を管理する必要がありますが、資材置き場として貸している間は、基本的に借主が出入りすることになります。土地の管理も借主がしてくれるので、管理をする手間がなくなるでしょう。
6つ目のメリットは、売却しやすい点です。資材置き場は借地借家法が適用されないので、売却したい時は解約を申し出ることでスムーズに売却できます。
続いて、資材置き場のデメリットについて解説します。
1つ目のデメリットは、賃料の相場が低めである点です。建物を貸すアパート・マンション経営と違い、土地を貸すだけの資材置き場は賃料が低いのが一般的です。
年間収益のおおよその目安は、固定資産税額の5〜6倍程度と言われています。賃料を高くするのは難しいため、長期で契約してもらうことで、安定性でカバーするのが理想的でしょう。
2つ目のデメリットは、節税効果が低い点です。通常、住宅が建っている土地は住宅用地の特例が適用されるため、固定資産税や都市計画税が軽減されます。
しかし、更地はそれらの軽減措置を受けられないため、税負担が3倍〜6倍ほどになるのです。固定資産税や都市計画税の負担を少しでも減らすためには、そもそも土地を選ぶ段階で評価額の小さい土地を選ぶ必要があるでしょう。
また、資材置き場は相続税対策にも適していません。住宅が建っていないので、「小規模宅地の特例」などの相続税の軽減措置が適用されないためです。
ただし、例外として土地活用の専門業者に土地を貸す場合は、相続税の減額対象となることがあります。とはいえ、住宅を貸す場合と比べると減額率は低いです。
3つ目のデメリットは、借り手が見つからない可能性がある点です。
資材置き場を必要とする個人や企業はそう多くないため、タイミング次第では借り手が見つからないことがあります。近くで工事をしている業者がいれば、短期的に貸し出せますが、工事が終われば契約も終了です。
そのため、借り手を探すのであれば、できるだけ長期的に利用する見込みが高い業者を探す必要があります。オーナー自身が自分で探すのはハードルが高いので、地場に強い不動産会社に依頼し、営業をかけてもらうといいでしょう。
4つ目のデメリットは、近隣トラブルが発生する可能性がある点です。
資材置き場には工事で使う砂や砂利の他、さまざまな資材が保管されます。トラックが頻繁に出入りするため、風向きによってはそれらが近隣の住宅地に飛来し、住民から苦情が来る可能性があります。
特に大規模な工事がある場合は、業者が開催する住民向けの説明会に参加し、資材置き場の場所やその影響など、事前に説明してもらうようにしましょう。
また、業者側にも資材の運搬時はカバーを利用することや、近隣住民への配慮をしてもらうように、事前に声かけをすることをオススメします。
自動販売機の設置

自動販売機を設置して収益化をはかる活用方法です。初期投資を抑えやすいだけでなく、変形地や狭小地でも実現しやすいのが特徴になります。
自動販売機の1つ目のメリットは、狭いスペースを有効活用できる点です。
自動販売機は幅100cm、奥行きが70cmもあれば設置できます。他に使い道がないような狭い土地でも、自動販売機であれば収益化を目指すことが可能です。
2つ目のメリットは、初期費用を抑えやすい点です。
自分で購入する場合、50万円前後の初期投資で始められますし、飲料メーカーに場所を貸すだけの場合、販売機は無償で借りられるため、初期投資は必要ありません。
3つ目のメリットは、手間がかからない点です。
作業が発生したとしても周辺の掃除くらいであり、販売機のメンテナンスは基本的に全て業者に任せられるため、極めて手離れが良い活用方法と言えます。
続いて、デメリットは以下の通りです。
1つ目のデメリットは、収益性が低い点です。飲料メーカーに場所を貸すだけの場合、月々に得られる賃料はおおよそ5千円前後になります。
自分自身で販売機を運営する場合は、売上に応じて収入が増えますが、それでも他の賃貸経営と比べると収益性は劣ります。ローリスクかつローリターンの活用方法であることを覚えておきましょう。
2つ目のデメリットは節税効果を期待できない点です。自動販売機は建物ではないので、税制上は更地の状態と同等になります。
住宅が建っていないのであれば、住宅用地の特例が適用されないため、固定資産税や都市計画税の軽減措置を受けられません。
3つ目のデメリットは、収益性が低い割にランニングコストがかかる点です。
自動販売機の動力は電気ですので、毎月電気代がかかります。特に冬場は電気代が高くなりがちで、月に数千円かかることもあります。
自動販売機はそもそも収益性が高くないので、こうしたランニングコストによって利益が圧縮される可能性があるでしょう。
4つ目のデメリットは、販売機が壊される可能性がある点です。
治安の悪いエリアに販売機を設置してしまうと、落書きをされたり、最悪の場合、破壊されてしまう可能性があります。手離れが良い活用方法とはいえ、被害を防ぐためには、最低限の管理が必要です。
土地信託
土地信託とは、信託会社に土地の運営を託し、発生した収益の一部から配当金を受け取れる活用方法です。オーナー側が初期投資をする必要がなく、ローリスクな活用方法の1つと言えます。
土地信託の種類には大きく「賃貸型」と「処分型」の2つがあります。
賃貸型は、オーナーと信託会社が信託契約を結び、信託会社の運用によって発生した利益の一部から信託配当金を受け取るものです。
なお、一般的に「土地信託」と呼ばれるものは賃貸型であるケースが多いです。賃貸型では、契約期間が終了すると、オーナーの元に土地が返還される特徴があります。
一方で処分型は、売却によって土地を手放すものです。単純に売却するのではなく、信託会社の開発・運用によって付加価値を上乗せした状態で売却するため、信託する前よりも高い価格で売却しやすい特徴があります。
土地信託の1つ目のメリットは、オーナー自身に経営知識が不要である点です。
土地信託は、活用方法の選択から運用に至るまでを全て信託会社がおこないます。そのため、オーナー自身に経営の経験や知識は不要です。ただし、提案された活用方法の是非を判断できる程度の最低限の知識はあった方が良いでしょう。
2つ目のメリットは、建物付きで土地が返還される点です。
土地信託では、信託会社がローンを借り、アパート・マンションや商業施設などの建物を建設します。そして、契約期間が終了した際、オーナーは建物も込みで土地を返してもらうことができるのです。
ただし、ローンの残債がある場合は残債ごと引き継ぐことになります。ローンの返済が完了した状態で契約期間が終了し、土地と建物が返還されるのが理想的と言えるでしょう。
3つ目のメリットは、初期投資が不要である点です。
土地信託では、初期投資の負担をすべて信託会社が負うことになります。信託会社に信託報酬を支払う分、収益性が下がるのはデメリットですが、オーナー自身が金銭的なリスクを負わずに収益を得られる点は大きなメリットです。
4つ目のメリットは、節税効果を期待できる点です。
土地信託によって土地の所有権が信託会社に移る代わりに、オーナーは信託受益権を得ます。そして、土地信託の契約期間中に相続が発生した場合、相続人は所有権ではなく信託受益権を相続するのです。
土地の所有権の相続と比べて、信託受益権の相続は相続税を節約しやすく、手続きも簡易的になります。
続いて、土地信託のデメリットは以下の通りです。
1つ目のデメリットは、必ず配当金が得られるわけではない点です。信託配当金は、信託会社が土地を運用して発生した収益の一部から支払われます。
そのため、そもそも運用に失敗して収益が少なかったり、経費が多いために利益が少なかったりすると、配当金の支払いもありません。
2つ目のデメリットは、自分で運用する場合と比べて収益性が下がる点です。
土地信託では信託会社に活用の全てを任せる代わりに、信託報酬を支払う必要があります。なお、運用で発生した収益から経費や信託報酬を引いた金額は、おおよそ収益の5%〜20%と言われています。
3つ目のデメリットは、土地信託を実現できる土地が限られているという点です。
土地信託はどのような土地でも無条件におこなえるものではありません。簡単に言えば、信託会社が「自社の利益になる」と判断できるような土地でなければ、そもそも信託契約を結ぶことができないのです。
しかし、収益が上がるポテンシャルがある土地なのであれば、オーナー自身が活用した方が収益性は断然高くなるでしょう。「手離れの良さ」を取るか、「収益性」を取るか、オーナーの経営判断が求められます。
等価交換
等価交換とは、ディベロッパーと呼ばれる開発業者と特殊な契約を結ぶことで、 オーナー側が建築費用を負担せずに土地活用ができる方法です。主にマンションやオフィスビルなどの大型の建物を建てる際に用いられる手法と言えます。
また、等価交換はオーナー側からの提案ではなく、ディベロッパー側からの提案であることが一般的です。
契約内容としては、まずディベロッパーが費用を負担して建物を建てます。その後、建物の所有権の一部と土地の所有権の一部を等価で交換するのが等価交換です。つまり、互いに建物と土地の所有者になり、一蓮托生の関係になります。
等価交換の1つ目のメリットは、金銭的なリスクを負わずに大きな事業に参画できる点です。
資金の借入れはディベロッパー側がおこなうため、土地オーナーは借入をする必要がありません。仮に事業の収益が減ったとしても、返済リスクがないため、ローリスクで運用できます。
2つ目のメリットは、譲渡所得税の繰延べができる点です。
等価交換は事実上の土地売却であるため、通常であれば利益が出た際に譲渡所得税が発生しますが、『買い替え特例』を利用することで譲渡所得税の繰延ができます。
3つ目のメリットは、土地活用の知識がない状態で大規模な運用ができる点です。
等価交換では、土地の運用をディベロッパーが全て代わりにおこなってくれます。活用方法の選択や、マーケット調査、集客や管理など、ディベロッパーには豊富な知識と経験があるので、オーナー側は安心して任せることができます。
続いて、等価交換のデメリットは以下の通りです。
1つ目のデメリットは、好立地でないとそもそも声がかからない点です。
等価交換ではディベロッパー側が巨額の投資をします。つまり、投資した以上のリターンが見込めるような土地でないと、そもそも声をかけてもらえないのです。好立地で広く、さまざまなビジネスチャンスがある魅力的な土地でなければ、等価交換を実現することは難しいと言えるでしょう。
2つ目のデメリットは、還元床の調整が難航しやすい点です。
還元床とは、オーナー側とディベロッパー側がそれぞれ占有する竣工後の床面積を指します。難航しやすい理由は、還元床面積が広いほどより多くの家賃収入を得られるためです。オーナー側もディベロッパー側も収入は多い方がいいので、利害の対立が起こりやすいと言えます。
3つ目のデメリットは、権利が複雑になる点です。
オーナーとディベロッパーで建物も土地も共有することになるため、管理や売却、建て替えなどの話を進める際に、利害が対立しやすい傾向があります。
売却
自分で土地を運用したり、業者に貸したり信託したりせずに、売却して売却益を手に入れるのも手です。
売却の1つ目のメリットは、資産の組み換えができる点です。売却によって得た資金を有効活用すれば、収支の改善につながります。
具体的には借入の返済、株式や外貨の購入、別の不動産の購入などです。上手くいけば、売却前よりも収入を増やすことも可能でしょう。
2つ目のメリットは、固定費の負担を軽減できる点です。土地を手放せば、固定資産税や都市計画税の支払いをせずに済みます。
売却のデメリットは以下の通りです。
まず、収入源であった土地の所有権を手放すため、収益の機会を失います。2つ目のデメリットは、売却益がそのまま手元に入ってくるわけではない点です。
譲渡所得税や仲介手数料、印紙税の支払いをする必要がある他、場合によっては測量費が発生することもあります。1億円で売却できたとしても、1億円の収入となるわけではないので注意が必要です。
3つ目のデメリットは、所有期間によって譲渡所得税の負担が大きく変わる点です。譲渡所得税とは、不動産の売却益に対して課される所得税や住民税の総称を意味します。
税率は土地の「所有期間」によって大きく異なるため注意が必要です。所有期間ごとの税率は以下の表を確認して下さい。
| 所有期間 | 所得税の税率 | 住民税の税率 | 復興特別所得税の税率 |
| 5年以内 | 30% | 9% | 0.63% |
| 5年を超える | 15% | 5% | 0.315% |
なお、土地を売却する時期の見極め方や注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。

土地の寄附

使う予定のない土地は、寄附をすることもできます。代表的な寄附先は自治体です。
事前に窓口に相談すると、土地の調査がおこなわれ、調査内容を元に寄附を受けるかどうか審査します。審査通過後に必要書類を提出すれば、寄附は完了です。
寄附の主なメリットは、贈与税が発生しない点です。贈与税はおよそ評価額の10%程度になると言われており、土地の評価額が高いとかなりの負担になります。
実際、贈与税の負担を嫌がられて、贈与を拒否されるケースも少なくありません。その点、自治体に寄附できれば贈与税の心配がいりません。
寄附の主なデメリットは、審査制である点です。自治体としても活用することを前提に寄付を受けるため、そもそも活用が難しい土地だと審査で落ちる可能性が高いでしょう。
自治体にとって土地所有者からの固定資産税は貴重な財源です。活用が難しい土地を引き取って不要な管理コストがかさむよりも、そのまま所有してもらって税金を納めてもらった方が安泰と考えても不思議ではありません。
寄付を受け付ける判断基準は自治体によって異なりますが、少なくとも活用の選択肢があること、公共的な活用が可能であることが重要と言えるでしょう。
地方と都市を比較!どちらの土地が利益を出しやすい?

こちらでは、「地方の土地」と「都市の土地」、どちらがより利益を出しやすいのかについて解説します。
地方と都市はどちらの土地が利益を出しやすい?
地方の土地と都市の土地を比較すると、利益を出しやすいのは「都市の土地」になります。なぜ都市の方が利益を出しやすいのか、地方と都市を比較した表は以下の通りです。
| 比較基準 | 地方 | 都市 | 違い |
| 競合 | 少ない | 多い | 多い方が賃料を上げやすい |
| 商圏の範囲 | 狭い | 広い | 広い方が市場が大きい |
| 人口 | 少ない | 多い | 多い方が売り上げの見込みを立てやすい |
| アクセス | しにくい | しやすい | 公共交通機関が近くにあると人が集まりやすい |
以上の観点から、土地活用をする上で地方よりも都市の方が利益を出しやすいと言えます。
ただし、地方でも都市に負けないくらいの利益を出せる可能性もあります。
例えば、インターの降り口周辺の土地や国道と国土の角地などは車通りも多く、コンビニや飲食店など、需要とマッチすれば都市に匹敵する利益を出せる見込みはあるでしょう。
地方の土地の活用方法
利益の出しやすさでは都市に劣る地方ですが、地方ならではの活用方法がいくつか存在します。そこで、こちらでは地方特有の活用方法を2つ紹介します。
貸し農園
地方の土地活用の代表格と言えば、貸し農園です。高い収益性は期待できませんが、使っていない土地の固定資産税をまかなう程度の目的であれば、有効な活用手段と言えます。
貸し農園には大きく2つの種類があるので、それぞれ紹介します。
・市民農園
市民農園とは、農地を区分けして貸し出すタイプの農園です。利用者は基本的に農業経験者であるため、苗や農具などの必要な物は利用者が自分で用意します。
オーナーの主な仕事は土地の区分け、賃貸借契約の手続き、簡易的な管理作業くらいなので、手離れの良いやり方です。
市民農園には、宿泊施設と併設した「滞在型」も存在します。年単位で農地を貸し出し、賃料を得るものです。
通常の市民農園と比べて利用料の相場が高い特徴がありますが、一方で宿泊施設を建てるために初期投資がかかります。投資額を回収できる見込みがあれば、検討してみてもいいでしょう。
・体験農園
体験農園とは、農業初心者向けに農業体験を提供するタイプの農園です。作物の栽培や農地の管理はオーナーがおこなう必要があるため、市民農園よりも手間がかかります。
その代わりに、区分けで貸すサービスではなく時間貸しのサービスなので、集客力次第では市民農園よりも売上を伸ばしやすいでしょう。
貸し農園のメリットは以下の通りです。
1点目のメリットは、初期投資の負担が小さい点です。農地さえあれば、ほとんど手を加えずにすぐにでも始められるため、他の活用方法と比べてかなり始めるハードルが低いと言えます。
2点目のメリットは、立地が悪くても成立する点です。賃貸住宅や商業施設のように、アクセスが良い必要がなく、むしろ貸し農園はひと気がない静かな地方や郊外の土地の方が需要があります。
3点目のメリットは、資産価値の低下を防ぎやすい点です。農地を放置していると、雑草が生い茂ったり、害虫が発生したりして荒れがちです。土地の資産価値が低下する原因となるため、収益性が高くなくても活用するメリットはあります。
4点目のメリットは、固定資産税を賄うことができる点です。遊休農地は通常の農地や建物が建っている土地と比べて、固定資産税の負担が大きい傾向があります。有効活用することで収益を固定資産税の支払いに充当できれば、赤字を垂れ流しを防ぎやすくなります。
続いて、貸し農園のデメリットは以下の通りです。
1点目のデメリットは、高収益を狙いにくい点です。貸し農園の利用料の相場は、高くても1万円程度になります。
売上は農地の広さやエリアによって異なりますが、年間数百万円規模の売上を目指すのは現実的とは言えないでしょう。初期投資の負担が小さくローリスクである反面、ローリターンであることは覚えておきましょう。
2点目のデメリットは、定期的なメンテナンスや巡回作業が発生する点です。
貸し農園は他の活用方法と比べて手間がかからないですが、それでも最低限の労力はかかります。集客に苦戦して利用者がいない場合は、手入れをしないと土地が荒れてしまいますし、荒れた状態を放置すればますます利用者が増えなくなってしまうでしょう。
3点目のデメリットは、開始前に自治体や農業委員会への届出が必要である点です。
どういうスタイルで貸し農園を経営するかにもよりますが、自治体や農業委員会の承認を得るまでに一定期間を要する他、計画書の作成を求められる場合もあります。
資材置き場
地方の土地で、資材置き場は有効な活用方法の1つです。規制が強い市街化調整区域や農地法の対象となっている土地でも活用できます。
メリットは、手軽に始められる点と、将来的に別の活用に変更しやすい点です。最低限土地が整備されていれば、ほとんど初期費用をかけずに始められます。
まだ本腰を入れて活用をするつもりがない場合や、とりあえず固定資産税分だけでも収益化したい場合に向いているでしょう。
デメリットは、収益性が低い点です。建物を貸す場合と比べると賃料はかなり低くなっており、収益性を重視する方にはあまり向いていません。また、ある程度の広さがないと需要がない点もデメリットと言えるでしょう。
地方の土地活用についてより詳しく知りたい方は以下の記事を参考にして下さい。
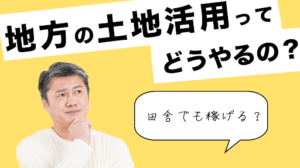
都市の土地の活用方法
続いて、都市の土地に向いている活用方法を2つ紹介します。
オフィスビルや貸店舗経営
オフィス街がある都市では、オフィスビルや貸店舗経営がオススメです。通常の賃貸住宅と違って借主が個人ではなく事業者なので、賃料を高めに設定しやすいのがメリットと言えます。
デメリットは、初期投資の負担が大きくなりやすい点です。オフィスや店舗には相応の広さが必要であり、収益性を高めるには階数も必要であるため、必然的に建築費用が高くなります。
また、賃貸住宅と違って戸数が少ないため、空室リスクが大きい点もデメリットです。
テナント兼賃貸住宅
テナント兼賃貸住宅とは、建物の低層階をテナントとして貸し出し、上層階を賃貸住宅として貸し出す方法です。
賃貸住宅において、低層階は日当たりの悪さやセキュリティ面から敬遠される傾向があり、上層階よりも賃料を下げないと借主が決まりにくいのが一般的です。
しかし、企業にとって住宅の低層階に店舗を出せることは、大きなメリットがあります。人目に触れやすく、集客に効果的だからです。賃貸住宅の低層階を企業向けに貸し出すことができれば、賃料も高めに設定しやすいため、建物全体の収益性はむしろ向上します。
ただし、飲食店に貸す場合は匂いや騒音に関して住民からクレームが届く場合があるので注意が必要です。
他にも都市で向いている土地活用には「ホテル経営」や「コインパーキング」などがあります。詳しく知りたい方は以下の記事を参考にして下さい。

狭い土地と広い土地を比較!どちらが利益を出しやすい?

こちらでは「狭い土地」と「広い土地」のどちらが利益を出しやすいのか、またそれぞれの土地に向いている活用方法は何なのかを解説します。
狭い土地と広い土地はどちらが利益を出しやすい?
狭い土地と広い土地で利益を出しやすいのは、広い土地です。なぜ広い方が利益を出しやすいのか、広い土地と狭い土地を比較した表は以下の通りです。
土地活用のビジネスの基礎知識を紹介
「維持費をまかなうことができる」というのも土地活用のメリットのひとつですが、取り組み方次第では土地活用にはそれ以上のメリットを期待できます。
こちらでは土地活用でビジネスを行うメリットとデメリットを紹介しましょう。
| 比較基準 | 広い土地 | 狭い土地 |
| 活用の選択肢 | 多い | 少ない |
| 駐車場 | 作りやすい | 作りにくい |
| 用途 | 商業施設や遊戯施設等、土地自体が目的地になりやすい | 駐車場や自動販売機等、目的地ではなく中継地点になりがち |
以上の観点から、狭い土地よりも広い土地の方が利益を出しやすいと言えます。
狭い土地の活用方法
こちらでは狭い土地にオススメの活用方法を4つ紹介します。
自動販売機の設置
狭い土地を収益化する活用方法の代表格が自動販売機の設置です。
幅が100cm、高さ2m、奥行きが70cmほどのスペースがあれば1台設置できるため、お手軽に始められますが、どこにでも自由に設置していいわけではありません。
まず、自動販売機は道路占有許可を受けられないため(道路法32条)、設置する際は販売機が道路にはみ出さないようにする必要があります(※2)。
また、景観との調和を重んじる地域では、条例によって色彩基準が決められているため、基準に応じたデザインの販売機を設置しなければなりません。
さらに、自動販売機はジャンルとしては小売ですので、最低限の売り上げが見込める立地でないと、収益化は難しいでしょう。維持費として電気代がかかるので、最悪赤字になってしまう可能性もあります。
賃貸アパート・マンションの空きスペース、近所にアパート・マンションがあるエリアであれば常に人が行き交うので、ある程度の売り上げを見込めるでしょう。
自動販売機を狭い土地に設置するメリットは、手軽さや初期投資の負担が小さい点以外にもあります。
夜間には照明代わりになるので、防犯対策として有効です。また、賃貸アパート・マンションの敷地内であれば、入居者の利便性を向上させることにつながるでしょう。
デメリットは、設置場所を誤ると、飲料の落下音や取り出し時の音が騒音となり、入居者や近隣住民から苦情がくる可能性がある点です。
また、飲み終わったペットボトルや空き缶などのゴミが散乱したり、自販機荒らしの被害にあったりする可能性もゼロではありません。
治安が悪いエリアに自動販売機を設置する場合は、定期的な監視や何らかの防犯対策が必要でしょう。
看板用地
狭い土地の活用方法として、自動販売機よりもさらに手軽に始められるのが看板用地です。看板を設置したい事業者に空き地を貸し出すことで、毎月看板提出料を得ることができます。
一般的には「広告募集中」という看板を設置しておき、事業者側から問い合わせをもらうケースが多いです。視認性が高い土地であれば、地方でも十分需要があるでしょう。
看板用地のメリットは、
・初期費用がかからない
・収益が安定しやすい
・別の用途への転用がしやすい
などがあげられます。
看板の製作・設置を借主側が負担すれば、初期費用はかからないですし、自分で看板を設置する場合もおよそ10〜15万円の費用で済みます。
デメリットは、収益性が低い点です。看板用地の賃料は年間で1万〜5万円が相場と言われており、固定資産税の負担を軽減する程度しか売り上げが見込めません。
また、放置し過ぎると看板が劣化して落下したり、強風で飛ばされて事故の原因となることがあります。
人や自動車、建物に何らかの被害を与えてしまった場合、損害賠償請求をされる可能性もあるでしょう。看板用地として活用する際は、定期的な点検やメンテナンスをおこなうことをオススメします。
狭い土地の活用方法についてより詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にして下さい。

証明写真機

狭い土地では証明写真機を設置するのも有効です。広さは0.3坪程度の面積があれば設置ができます。維持費は電気代くらいで、設置や管理も写真機の管理会社がおこなってくれます。
メリットは、同じ狭い面積を活用するのでも、自動販売機より高い収益を期待できる点です。飲料よりも単価が高く、年中需要がある点もメリットと言えるでしょう。
デメリットは節税効果を期待できない点です。住宅用地ではないため、固定資産税の軽減措置などを受けられません。
また、証明写真は土地柄によって需要に差があるため、自販機よりも立地が重要となります。証明写真を利用する機会の多い学生が多いエリアでは、高い需要を見込めるでしょう。
駐輪場経営
建物を建てられるほどの広さはないが、自動販売機を置くだけではもったいないような土地の場合、駐輪場として活用する方法があります。
駐輪場は、自転車1台あたり横2.5m、縦5mほどのスペースがあれば運営が可能です。具体的な運営方法としては、「月極」と「時間貸し」の2つがあります。
月極の場合は、簡易的な舗装や区画のラインがあれば問題ありません。時間貸しの場合は、看板や精算機、ゲートを設置する必要があるため、月極と比べて初期費用がかかります。
駐輪場のメリットは、建物を建てることなくそれなりの収益性を期待できる点です。固定資産税の負担以上の利益が見込める可能性があり、維持費の負担が軽くなるでしょう。
デメリットは、節税効果を期待できない点です。住宅用地ではないため固定資産税の軽減措置は受けられない他、建物を建てるわけではないので、建設費用を減価償却することもできません。
また、エリアによっては競合が多く、価格競争に巻き込まれる可能性もあります。そのようなエリアでは、極力初期費用をかけず、いつ撤退してもいいくらいの感覚で始めるのが妥当と言えるでしょう。
広い土地の活用方法
続いてこちらでは、広い土地にオススメの活用方法を3つ紹介します。
展示場
広い土地を所有している場合は、展示場としてハウスメーカーに貸し出す方法があります。ハウスメーカーは借りた土地にモデルハウスを建て、オーナーはメーカーから賃料を得るビジネスモデルです。
建物の建築・撤去費用はメーカーが負担してくれる上、管理や運営もメーカーがおこなうのが一般的なので、オーナー側は基本的に何もする必要がありません。
実際に人が住むわけではないので、居住権や借地権に関するトラブルが発生することもありません。
展示場のメリットは、契約が終了したら建物を撤去して更地の状態で返還してもらえる点です。短中期で暫定的に活用する手段としては都合がいいと言えます。
一方で、契約期間が長くなりがちである点はデメリットです。契約期間は5年以上になることも珍しくなく、その期間は土地を自由に活用できません。
広い土地の活用の選択肢は他にもあるので、ハウスメーカーからの提案を受け入れるかどうかは慎重に検討しましょう。
土地貸し
長期で安定した収益を得たい人には、土地貸しがオススメです。
土地貸しとは、ドラッグストアやスーパー、ホームセンターなど、売り場面積が比較的大きい店舗を必要とする企業に土地を貸すことを言います。
「借地」と呼ばれ、10年〜20年くらいの長期で貸し出すことが一般的です。
オーナー側は土地を貸すだけで、建物の建設費用は企業側が負担するため、初期投資の負担も抑えられます。建物を貸すよりも賃料は安くなりますが、知名度の高い企業と契約できれば、長期的に安定した収益を期待できるでしょう。
まや、契約終了後は企業側で建物を撤去してから更地の状態で返還されるので、原状回復を巡るトラブルの心配もいりません。なお、土地貸しには契約方法によって種類がいくつかあります。
それぞれのメリット・デメリットについては以下の記事を参考にして下さい。

医療施設

十分な広い面積があれば、医療施設を建設して貸し出す活用も可能です。土地周辺に人が住んでいれば、郊外でもニーズがあります。日本は超高齢化社会ですので、医療施設の利用者は今後ますます増えていく可能性が高いでしょう。
メリットは、医療施設が地域に定着すれば長期的に安定した収益を見込める点です。
一方で、医療施設は社会的な役割や責任が大きいため、他の活用方法と比べて許可や手続き等が困難である点がデメリットです。
また、医療用に建てた建物は構造が特殊であり、他の用途への変更が難しいため、始める際は綿密な事業計画を立てて取り組む必要があります。
広い土地の活用方法についてより詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にして下さい。

【2023年版】近年注目の土地活用
冷凍餃子の無人販売所
2021年から2022年にかけて、急増したのが「冷凍餃子の無人販売所」です。郊外にあるコンビニやスーパー近くで、ガラス張りの店舗を見かけたことがある人もいるでしょう。
利用者は冷凍庫から商品を取り出し、支払い方法は賽銭箱のような入れ物に現金を投入するだけというシンプルなシステムです。防犯カメラこそついているものの、治安が良い日本だからこそ成立する営業形態と言えます。
冷凍餃子の無人販売所の代表格と言えば、「餃子の雪松」です。2018年には1号店を開いた雪松ですが、2023年1月の時点で店舗数は432店舗まで増えています。
商品力はもとより、ここまで急速に拡大した背景は新型コロナウィルス感染症の影響で、非接触性の店舗へのニーズが高まったことや巣篭もり需要の拡大が挙げられるでしょう。
冷凍餃子の無人販売所のメリットは、ランニングコストを大幅に抑えられる点です。照明や冷凍庫のために電気代こそかかるものの、人件費を1円もかけずに24時間営業ができます。また、駅前や中心街など、好立地でなくとも成立する点もメリットです。
さらに、無人販売所は話題性があるため、SNSで勝手に拡散されたり、ローカルメディアからの取材が入ったり、販促費用も節約しやすい傾向があります。
デメリットとしては、肝心の商品を作る開発力や工場設備を有する必要がある点です。
店舗開発のハードルは低いですが、大量の商品を製造するための初期投資はかなりの負担と言えます。参入ハードルが低く見えがちですが、商品開発力や資本力がないと勝ち残るのは難しいでしょう。
同じ事業をゼロから始めるよりも、無人販売事業を営む企業に対してテナント貸しをする方が無難と言えます。
体験型のリゾート
新型コロナウィルス感染症の影響で、日本中のレジャー施設が閉鎖に追い込まれる中、独自のコンセプトと戦略で大奮闘を見せているのが「ネスタリゾート神戸」です。
「大自然の冒険テーマパーク」を謳っており、約230㎡に及ぶ広大な敷地内では、キャンプ、グランピング、キャニオ・ドロップ、ワイルド・カヌー、ボルダリングなど、さまざまなアクティビティを体験できます。
また、ネスタリゾートはホテルや温泉も併設されており、ディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンに次ぐ、新たなリゾート施設として期待されています。2022年第1四半期には過去最高の売上を更新しており、ますます勢いを増していくでしょう。
ネスタリゾートほど大規模ではないにしても、このような体験型の施設は今後ニーズが拡大していく可能性があります。
メリットは、国内だけでなく海外のインバウンド需要も取り込める可能性がある点です。日本総研の調査によれば、訪日外客数が2023年末に2000万人を超える水準まで回復するとされており、リゾート市場もその恩恵を受けられる可能性はあるでしょう(※3)。
デメリットは、莫大な初期投資が必要である点です。いち個人や中小企業がネスタリゾートのような規模のリゾート施設を始めるのは中々非現実的と言えるでしょう。
ただし、規模や工夫次第では体験型の施設を始めることも不可能ではありません。例えば、北海道では廃校になった校舎をリノベーションして、体験型の環境教育プログラムの拠点にするといった活動がおこなわれています。
このように、視点を変えてターゲットや商圏を選ぶことで、体験型施設はさまざまな形で実現できると言えるでしょう。
※3「わが国のインバウンド需要に本格回復の兆し」(日本総研)
コンビニ経営
コンビニ経営と聞くと、フランチャイズに加盟して自分がオーナーになり、アルバイトを雇用してコンビニを経営するものと思う人もいるかもしれません。しかし、土地活用におけるコンビニ経営は少し様相が異なります。
経営方法は主に次の2つです。1つは「リースバック」で、オーナーが建物を建ててコンビニ業者に貸し出すものです。もう1つは「事業用定期借地」で、こちらは土地のみをコンビニ業者に貸し出し、建物をコンビニ業者が建てるものになります。
弊社は事業用定期借地によって全国でコンビニ経営をしています。その一部が以下のものです。
現在はコンビニエンスストアとして活用中の大阪府の土地です。コンビニエンスストアは建物や内装等の型がある程度決まっているため、工期は4ヶ月ほどで完了しました。
コロナ禍の影響で一時は売上が低迷していたコンビニ業界ですが、セブン&アイ・ホールディングスが発表した2022年3月〜11月の連結決算によると、純利益が同期で過去最高を記録しました。2023年2月期の通期予想も上方修正しており、好調ぶりがうかがえます。
コンビニ経営の大きなメリットは、収益性の高さです。安定して高い収益を生み出せる見込みが高いため、リースバックでも事業用定期借地でも、高い賃料を設定しやすい特徴があります。
エリアの需要によって賃料にはばらつきがありますが、同じ広さの賃貸住宅の数倍の賃料となることも珍しくありません。
デメリットは、出店エリアがある程度限られてしまう点です。
収益性が高いことがメリットであるコンビニですが、それを実現させるためには集客しやすい立地であることが最低条件です。特に事業用定期借地の場合は、コンビニメーカー側に「ここに出店したい」と思ってもらえないと実現は難しいと言えます。
また、コンビニの経営状況次第では賃料の減額交渉をされる可能性がある点もデメリットです。実際、弊社も同様の経験があります。
さらに、節税効果が薄い点もデメリットと言えるでしょう。相続税の優遇措置は多少あるものの、賃貸住宅が建っているわけではないので、住宅用地の特例を受けられず、固定資産税や都市計画税の軽減措置を受けられません。
固定資産税に関しては、単純計算で住宅用地の6倍の負担になります。コンビニ経営を始めるのであれば、こうした月々の支出を含め、収支のシミュレーションをしっかりおこなった上で始めることをオススメします。
老人ホーム経営
厚生労働省の調査によると、2014年から2020年にかけて、有料老人ホームの施設数は9632軒から15956軒まで増えており、年々増加傾向にあります(※4)。
老人ホームは土地活用の選択肢としても有効で、介護事業者に建物の一棟貸しをすることで賃料を得ることが可能です。
なお、介護事業者は利用者からの利用料だけで収益を上げるわけではありません。他の活用方法と大きく異なるのは、収益の大部分が自治体からの「介護報酬」である点です。
そもそも介護サービスにおいて、利用者負担は原則として1割と決められています。それだけだと事業が成立しないため、残りの9割を自治体からの介護報酬によって補っているのです。
つまり、老人ホーム経営では利用者の入居状況だけでなく、介護報酬の改定も経営状況に大きく影響を与えます。だからこそ介護事業者に建物を貸すオーナーは、それらの影響で家賃の減額交渉があるリスクや、退去するリスクを想定しておく必要があります。
老人ホームを経営するメリットは以下の通りです。
まず、介護事業者への一棟貸しのため、収益が安定しやすいメリットがあります。原則として賃料は固定であるため、アパート・マンションのように空室を埋めるために賃料を下げるなどの対策が必要ありません。
また、アパート・マンションや商業施設、オフィスビルほど立地条件が厳しくない点もメリットです。駅から離れた土地であっても、近くにバス停があれば老人ホーム経営は成立すると言われています。
さらに、建物を建てにくいために敬遠されがちな市街化調整区域や第一種低層住居専用地域でも、老人ホームであれば建設が可能です。
それらの区域に該当する広い土地を所有しているのであれば、老人ホーム経営はかなり現実的な活用方法と言えます。
デメリットとしては、介護事業者の経営状況が介護報酬の改定の影響を受けやすい点です。改定によって経営が悪化すれば、賃料の減額交渉をされたり、最悪の場合は倒産したりする可能性があります。
また、始めるハードルが高い点もデメリットでしょう。老人ホームの建設には広い土地と資本力が必要です。
さらに、老人ホームや介護施設は建物の構造が特殊であるため、他の用途に変更しづらいという側面があります。万が一介護事業者が退去してしまったら、基本的には新たな借り手となる介護事業者を探す他選択肢がありません。
老人ホーム経営は、超高齢化社会の日本において非常にニーズがある事業と言えますが、相応のリスクがあることも念頭に置いておく必要があります。
シェアサイクル

シェアサイクルとは、自転車をレンタルできるサービスのことで「レンタルサイクル」と呼ばれることもあります。
国土交通省の調査によれば、導入している都市数は日本が世界3位であり(2019年時点)、自転車が設置されるポートの数は2015年から2018年にかけて約4.6倍まで拡大しました(※5)。
シェアサイクルは駅前やコンビニ前、公園や役所前、観光地など、さまざまな場所に設置されています。利用者は事前登録を済ませておくことで、自由に自転車を借りることが可能です。
必要な設備や自転車の用意はシェアサイクルメーカーがおこなってくれるため、オーナーは土地を貸すだけで毎月賃料を得ることができます。
メリットは、狭くて活用しにくいデッドスペースがある土地でも実現しやすい点です。
土地だけ貸せば管理や運営、カスタマーサポートなども全てメーカー側が対応してくれるため、手離れが良い点もメリットと言えるでしょう。
デメリットは収益性が高くない点です。建物を貸すわけではなく、貸せる土地の面積も広くないので、必然的に収益は低くなります。
ある程度人通りが多く、活用方法が定まっていない場合の暫定的な活用方法として有効と言えるでしょう。
他にもキャンプ場として活用する事例もここ数年増えつつあります。キャンプ場としての活用に興味がある方は、以下の記事を参考にして下さい。

土地活用ビジネスのリスクを回避するには?
土地活用ビジネスを始める以上、どのようなリスクがあるのかを知っておくことは、オーナーであることの最低条件といえるでしょう。
土地活用において想定できるリスクや、回避する方法についてまとめたので、以下の内容を参考にしてください。
土地活用ビジネスの4つのリスクと回避方法
土地活用ビジネスをおこなっていくには、リスクを伴います。こちらでは、そのリスクと回避方法について解説していきます。
リスク1:市場に左右されやすい
土地活用は数年〜数十年と、長期にわたって経営するのが一般的です。数十年も経てば、当然景気の波はありますし、人の流れや土地の状況も変わるでしょう。
例えば、土地の近くに大学があり、大学生の入居が見込めるという理由で賃貸マンションを始めたのに、数年後にはその大学が廃校になり、空室が増えてしまうといったケースです。
あるいは、ロードサイドでテナント貸しをしていたところ、交通網が改変されたことで人の移動の流れが変わり、固定客が離れてしまうといった展開も考えられるでしょう。
市場リスクが与える影響は他にもあります。例えば、建物の修繕やリフォームをする際、材料の一部の価格が高騰していて、想定外の出費となるケースです。
2021年には「ウッドショック」が起こり、木材の価格が高騰しました。新型コロナウィルスの影響で在宅の需要が増え、中国やアメリカで住宅ブームが起きたことや木材を輸送するためのコンテナ不足などが主な原因です。
木材の供給が追いつかず、アメリカでは木材の価格が1年で6倍になりました。そして、その影響により、日本に輸入される木材も価格が高騰したのです。
他にも、例えば金融機関からの変動金利でローンを引いている場合、途中で金利が上昇してしまうというリスクも考えられます。
以上のように、土地活用をしていれば、何かしら市場の影響を受ける可能性があります。重要なのは、想定可能なリスクを把握しておくこと、そしてリスクが表面化したときのための準備をしておくことです。
事前に土地周辺の都市計画を細かくチェックしておく、利益が出ても無駄遣いせず内部留保にしておくなど、万が一の危機に備えておくことをオススメします。
リスク2:売却したくてもできない
土地活用において、最終的に土地や建物の「売却」を目的としているオーナーは少なくありません。しかし、買い手にとって適性な価格ではなかったり、買い手にとって不要な建物があったりすると、売れにくい傾向があります。
解体工事には膨大な費用がかかりますし、更地のほうが活用の選択肢が多いため、買い手にとって都合がいいのです。
また、土地や建物の価値が下落していれば、売却時に価格を下げざるを得ません。そのせいで売り手の希望価格を大きく下回れば、仮に売却できてもローンの残債が発生してしまうでしょう。「売りたくても、売ったら損をするので売れない」というジレンマに陥るのです。
売却できなければ、引き続き税金の支払いや維持管理の費用が発生しますから、あくまでも売れないリスクを想定した上で、売却スケジュールを組むことをオススメします。
リスク3:自然災害のリスク
土地活用でビジネスをするには、土地や建物が正常に機能していることが肝心です。土地が荒れていれば整備や造成工事が必要ですし、建物が老朽化していれば修繕するか建て直す必要があります。
しかし、そのような軌道修正が難しい場合もあるでしょう。地震や火災、水害といった自然災害に遭い、土地や建物が甚大な被害を受けた場合です。
仮にローンで建てた建物が修復不可能になったり、全壊してしまったりすれば、借金の支払いだけが残ってしまいます。こういったリスクに備えるためには、その土地の地形や気候の特性などを事前に調査することが必要です。
可能な限り災害時に大きな被害を受けないような造りにするし、保険に加入しておくなど、何重にも対策をしておきましょう。
リスク4:金利のリスク
土地活用において金融機関のローンを利用する際、一般的には「固定金利」と「変動金利」の2種類から選ぶことができます。どちらを選ぶかによって、リスクの内容が変わります。
まず固定金利は、景気の良し悪しにかかわらず金利が一定であるのがメリットです。金利を含む総支払額が先にわかるため、事業計画が立てやすいでしょう。
しかし、固定であるのと引き換えに、「金利が高い」というデメリットもあります。変動金利と比べ、およそ1.5倍ほどになることが多いといわれています。将来的に金利水準が下がったとしても、固定金利は借入時の利率のまま変わりません。
一方、変動金利はその名の通り、金利が変動します。政府の金利政策次第で金利水準が変わるため、金融機関は年に2回(4月と10月)に金利を見直すのです。
見直しによって金利が下がることもあれば、逆に金利が上がり、返済額が当初より増えるリスクもあります。固定金利と変動金利、両方の性質を十分に理解した上で、事業計画を立てましょう。
土地の特性を考慮して最適な土地活用する

土地活用ビジネスにおけるリスクは、前述の4つだけではありません。土地の特性に合った最適なビジネスモデルを選ばなければ、自らリスクを招き寄せてしまう場合もあります。
土地活用は、商品やサービスを売って利益を得るのではなく、「場」を提供することで収益化を目指すビジネスモデルです。
建物を建てる場合は数千万円、あるいは数億円単位の費用がかかるので、収益化ができていないからと、簡単には土地の用途は変更できません。
つまり、事前に土地の特性をよく理解し、最適な土地活用のビジネスモデルを選ぶ必要があるのです。
例えば、とある農地を相続して、そこで小さな宿泊施設を始めようと決めていたとします。しかし、自治体によっては、農地以外の用途に変更してはいけないケースがあるのです。
そういった事実を知らずに土地を相続すれば、事業計画は失敗となり、収益もできなくなります。
他にも、都市計画法によって定められた「市街化調整区域」と呼ばれるエリアでは、原則として新しい住宅や商業施設を建てることができないなど、建築物に対する制限が設けられていることがあります。
以上のように、自分が所有している土地でも、やりたいビジネスモデルを実現できるとは限りません。土地の相続や購入を決める前に、土地に関する法律や地域の特性を事前にしっかり調べておきましょう。
経営知識などの勉強をしておく
土地活用ビジネスのリスクを回避するためには、経営者としてのスキルも重要です。
といっても、大量に人を雇用して組織を運営するわけではないので、マネジメントスキルやリーダーシップなどのスキルはあまり重要ではありません。
例えば、「決断力」は土地活用においてあらゆる場面で求められるでしょう。
賃貸アパート・マンション経営やテナント貸しをする際、コストをかけてでも管理会社に管理業務を委託したほうがいいのか、それとも自分自身で管理して利益を最大化したほうがいいのか、決断を迫られることがあります。
あるいは、オフィスビルや商業施設を経営していて空室が続いていれば、賃料設定に悩む場面も出てきます。
1日でも早く空室を埋めるために賃料を低く設定したほうがいいのか、それとも高い賃料設定のまま新しい借り手が現れるのも待つほうがいいのか、短期的な利益と長期的な利益を天秤にかける場面もあるかもしれません。
どうすれば集客ができて、収益を増やすことができるのかといった知識が一番重要になってくるので、まずはそこを考えられるようになっておきましょう。
自分の考えでは不安な場合は、専門家に相談するのもひとつの手です。不動産投資や土地活用で実績のある会社に相談して、ビジネスとして土地の活用を成功させましょう。
他にも、土地活用を始める上でリスクを理解しておくことは非常に重要です。土地活用のリスクや回避法について知りたい方は以下の記事を参考にして下さい。

土地活用に関してよくある質問
最後に土地活用に関してよくいただく質問に回答します。
土地活用は誰に相談すればいい?
土地活用の相談先は、不動産会社やハウスメーカー、デベロッパー、工務店など様々な選択肢があり、相談内容や目的によって異なります。詳しくは以下の記事を参考にして下さい。

売れない土地の活用方法は?
活用のしようがなく、売ることも難しい土地は処分する必要があります。不要な土地を処分する具体的な方法を知りたい方は、以下の記事を参考にして下さい。
まとめ
土地活用のビジネスモデルは、人のニーズの数だけ存在します。そして、それらは立地や土地の広さによって最適なモデルが異なります。
そのため、オススメの活用方法は今どこにどのような土地を所有しているかによって答えが変わると言えるでしょう。
利益が出やすいという観点だけで言えば、「都市にある広い土地」「都市にある狭い土地」「地方にある広い土地」「地方にある狭い土地」という順位が妥当と言えます。
あとは各ビジネスモデルのメリットとデメリットを理解した上で、今所有している土地の価値を最大限引き出せるような選択をすることが重要です。
言い換えれば、これから土地を所有する人は目的から逆算して、どこのどのような土地を取得するか、どのようなビジネスモデルを選ぶかを検討するといいでしょう。
トチカツプロでは随時土地の買取を受け付けています。土地の売却や買い替え、活用方法などのご相談があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。