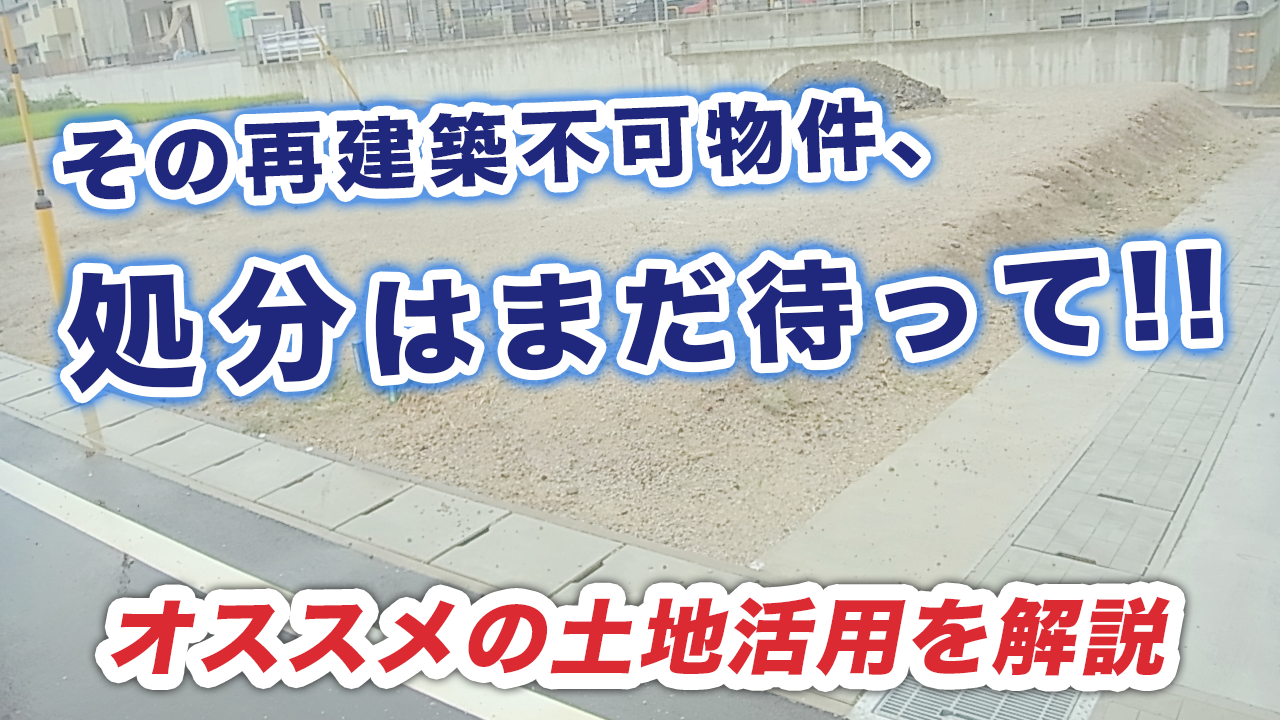再建築不可物件は、建物を新たに建設できないことから、土地活用において何かと敬遠されがちです。不動産としての価値も低く、中々買い手がつかないのも事実です。
しかし、一方で再建築不可物件は、工夫次第で有効活用できる可能性があります。
そこで、こちらでは再建築不可物件を購入するメリットやデメリット、オススメの活用方法について紹介していきます。
すでに再建築不可物件を所有している方、これから購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
再建築不可物件って?
こちらでは、まず再建築不可物件とはどのようなものなのかを解説します。
再建築不可物件とは
「再建築不可物件」とは、建築基準法上の要件を満たしていない土地に建てられた建物のことです。
なぜこのような物件が存在しているかというと、建築基準法が施行される以前に建てられた建物が残っているためです。
ここでいう「建築基準法条の要件」とは「接道義務」のことで、建築基準法では敷地と道路の関係を以下のように定めています。
- 敷地の間口が、2m以上道路に接している
- 接している道路の幅員が4m以上である
上記の接道義務を果たしていない土地に建つ建物は、再建築不可物件とみなされるのです。
災害時の避難経路を確保したり、救急・消防などの車両が通行しやすいように、このようなルールが定められています。
再建築不可かどうかを調べたい時は、管轄する役場の建築関連部署を頼るといいでしょう。
その際、法務局や登記所で、登記事項証明書や公図、建物の図面などを取得しておくと、スムーズに確認をしてもらえるはずです。
再建築不可物件はどれくらいある?
総務省による住宅・土地統計調査(平成30年)によると、東京の23区において、幅員2m未満の道路に接している住宅数が「18万2700戸」、敷地が道路に接していない住宅数が「5万9900戸」あります(※1)。
23区全体の住宅数が490万1200戸あるので、全体の約5%が再建築不可物件であることがわかります。
再建築不可物件で土地活用をするメリット・デメリットを解説
こちらでは、再建築不可物件での土地活用をする上での、メリットとデメリットについて解説します。
再建築不可物件を購入するメリット
・安価で購入可能
再建築不可物件を購入する一番のメリットは、安価に購入できる点でしょう。
再建築不可物件は土地活用をする上で非常に扱いにくく、同地域の同等の物件より、資産価値が低く見積もられる傾向にあります。
価格相場としては、同等の物件と比べて、およそ1割〜5割程度と言われているのです。
リフォームやリノベーションをする予定がある方にとっては、土地や建物を安価で購入できるチャンスといえるでしょう。
・土地の評価額が低いため、税負担が軽くなる
再建築不可物件は、用途が限定的であり、有効活用が難しいことから、土地の評価額が低くなる傾向にあります。
それに伴い、固定資産税や都市計画税、相続税や贈与税などの支払額も通常より安くなりやすいのです。
再建築不可物件を購入するデメリット
・不動産としての価値が低い
建物の再建築ができないため、用途がかなり限られてしまいます。事業活動によって収益を上げるのが困難であるため、不動産としての価値は基本的に低くなります。
・住宅ローンの審査に通りにくい
再建築不可物件は、換金性が悪いため、基本的に担保としての評価が低いです。そのため、住宅ローンの審査には通りにくいと言われています。ある程度の自己資金がなければ、購入は難しいでしょう。
・売却しにくい
建物の再建築ができず、融資を受けにくいという理由から、なかなか買い手が見つからない傾向にあります。売れたとしても、相場をかなり下回る価格になってしまうでしょう。
・使い勝手が悪い
そもそも接道義務を果たしていない土地のため、土地の特性上、使い勝手が悪い可能性があります。
たとえば、毎回隣地を通過しなければ、自分の敷地に入れなかったり、救急車や消防車、大型車両などが敷地内に進入できなかったりなどです。
・災害によって倒壊する恐れがある
再建築不可物件ということは、建築基準法が施行される前に建てられた建物ということです。
つまり、ただでさえ旧耐震基準である上、建物も老朽化している可能性が高く、災害などによって倒壊する恐れがあります。
もちろん、倒壊しても建物を再建築することはできないので、居住者がいる場合は退去せざるを得なくなりってしまいます。
再建築不可物件にオススメの土地活用
こちらでは、再建築不可物件でオススメの活用方法について解説します。
駐輪場の経営
接道義務の1つである「接している道路の幅員が4m以上」を満たしていない場合、駐車場として活用するのが困難となります。自動車のスムーズな進入が難しいためです。
ただし、「駐輪場」や「バイク用の駐車場」であれば、自動車ほどの広い間口は必要ないため、実現できる可能性があるでしょう。
土地周辺に駅や商業施設、駐輪場が完備されていない集合住宅などがあれば、需要があるかもしれません。
駐輪場に関しては、5坪程度の土地であれば、15台前後の駐輪が可能です。
バイク用の駐車場は、都市部でないと中々需要がないかもしれません。スペースとしては1台あたり奥行きが2m〜2.5m、横幅が1mほどの余裕があれば、そこそこ大型のバイクでも駐車できるでしょう。
また、最近では都心部を中心に、「シェアサイクル」が浸透しています。
国土交通省の調査によると、2019年時点で全国225都市に導入されているようです(※2)。
専門業者への土地貸しなので、初期費用ゼロで管理費用もかかりません。シェアサイクルサービスを展開する「PiPPA」では、申し込みから最短10日で利用を開始できるそうです(※3)。
立地条件がそこまで悪くないのであれば、更地にしてしまい、駐輪場やバイク用駐車場、シェアサイクルを運営してみてもいいでしょう。
太陽光発電
再建築不可の土地では、新たに建物を建てられませんが、太陽光発電のような設備を導入することは可能です。
そのため、建物を解体して更地にし、太陽光発電をおこなうことができます。あるいは、屋根の形状次第では、建物を解体せず、屋根に太陽光パネルを設置するという選択肢もあります。
発電した電力を電力会社に買い取ってもらうことで、収益化が可能です。
基本的には、一度設備を導入すれば、手放しで運営することができます。定期的にシステムの点検や簡単な清掃作業が必要ですが、それらの業務は専門業者に委託可能です。
地域の特性によって向き不向きはありますが、年間の日照量が毎年激しく変動するわけではないので、安定した運営ができるでしょう。
「売電価格が20年間固定である」という点もポイントです。事業を開始した年の価格が20年間ずっと固定される上、太陽光パネルの平均寿命も25年〜30年と言われています(※4)。
長期的に安定して収益をあげたい方に、オススメの活用方法です。
ただし、節税効果がない点と、固定価格が毎年下がり続けている点はデメリットと言えるでしょう。システムの導入費用はさほど安くなっていないにもかかわらず、固定価格が下がり続けているので、年々利回りが下がっています。
太陽光発電に関する詳しい情報は、こちらの記事を確認してみてください。

※4: 「2040年、太陽光パネルのゴミが大量に出てくる?再エネの廃棄物問題」(経済産業省 資源エネルギー庁
土地貸し
単純に「土地貸し」をおこなうという手もあります。もちろん、建物を建てることはできませんが、更地にして「資材置き場」として貸し出すことはできるでしょう。
立地次第では、資材置き場を探している建築業者もいるので、土地を貸すかわりに地代を得て、収益化できる可能性があります。
元々更地の状態であれば、建物の解体費用がかからないので、初期費用ゼロで始めることができます。
ただし、節税効果がない点、収益性が低い点はデメリットです。
土地の上に建物がない場合、固定資産税や都市計画税の軽減措置を受けられません。また、コインパーキングのように特別な設備を貸し出すわけでもないので、一般的に資材置き場の賃料は低くなりってしまいます。
次の活用方法が決まるまでの、暫定的な活用として検討してみてください。
自動販売機
自動販売機を設置することで、収益化するという方法もあります。
メーカーへの土地貸し形式であれば、初期費用を負担することなく始められます。収益性は決して高くないですが、立地次第では安定した収益を上げられるでしょう。
自動販売機を運営する方法は大きく2つです。
1つは「土地貸しタイプ」で、専用機器の設置場所をメーカーに貸し出し、地代を得るという方法です。
このタイプの場合、たいてい機材を無償貸与してもらえるため、初期費用ゼロで始めることもできます。
収益モデルとしては、賃料が月々固定のケースもあれば、売上に応じて賃料が変動するケースもあります。収益性は高くないですが、手離れの良さを重視する方にはオススメのタイプです。
もう1つの方法は「自営タイプ」で、オーナー自身が専用機器を購入し、設置します。中古だと20万円前後、新品だと最低でも50万円程度の予算が必要です(*5)。
また、仕入れや商品の補充も自分自身でおこなう必要があります。
初期費用や手間はかかりますが、収益性は基本的に「自営タイプ」の方が高くなります。
商品のラインナップや価格を自分で決められるのもメリットでしょう。売れ行きを観察して、利用者のニーズに合わせた運営ができます。
最近では、スイーツなどの変わった自動販売機も登場しており、珍しい商品を扱う自動販売機がメディアで取り上げられる機会も増えました。アイデア次第では大きな話題性が出る可能性があります。
再建築不可物件をうまく活用するポイントは?
最後に、再建築不可物件を上手に活用するポイントについて解説します。
土地の購入時に最低限のチェックをする
もし、これから再建築不可物件を購入する予定の人は、最低限、以下の項目をチェックするようにしましょう。
・インフラ環境に不備はないか
建物がある場合、水道や電気、ガスなどのインフラ環境が整備されているか、確認しましょう。不備があった場合、開設工事が必要になるため、余計なコストが発生してしまいます。
・雨水の排水に問題はないか
建築不可物件は、古い建物がほとんどです。雨水が地面にそのまま排水されていると、建物の基礎が傷んでしまうなどの被害が発生するおそれがあります. す。きちんと排水溝に流れているかどうか、確認しましょう。
・日当たりや風通しは悪くないか
再建築不可物件は広い道路に面していないため、立地上、複数の建物に囲まれているケースもあります。隣地の建物とすれすれの距離で、建物が建っているケースもあるでしょう。
そういった場合、日当たりや風通しが悪くなり、湿気が多くなったり、カビが発生したりする可能性があります。住居の場合はとくに使い勝手が悪くなってしまうので、日当たりや風通しは事前にしっかりチェックしましょう。
・車が入れる幅があり、駐車場ニーズがあるかどうか
駐車場として活用するつもりであれば、「車が進入できる幅があるか否か」「駐車場のニーズがあるか」の2点は、必ず事前に確認しましょう。
リフォームをする
何かとデメリットの多い再建築不可物件ですが、格安で購入できる点は大きな魅力です。
建物(住居)をリフォームすれば、自分で住んだり、賃貸物件として貸し出すこともできるでしょう。
ただし、リフォームを必ずできるとは限りません。自治体による建築確認を必要とする工事の場合、リフォームをおこなえないのです。
建築基準法では以下の条件に該当する場合、建築確認を必要としています。
- 第一号~三号の建築物を建築する
- 第一号~三号の大規模修繕もしくは大規模模様替え
- 第四号の建築
ここで重要なのは、「四号」に関しては「建築」のみ、建築確認が必要ということです。大規模修繕に関しては、とくに建築確認を必要としていません。
それぞれ、第一号〜四号までの定義は以下のようになっています。
- 一号 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの
- 二号 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
- 三号 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
- 四号 上記一号~三号以外の全ての建築物
つまり、延べ床面積や高さ、階数が一号〜三号の条件に該当せず、四号に該当する建物で、かつ増築・改築・大規模修繕であれば、建築確認は不要という解釈になります。
ただし、四号に該当する建物だとしても、無制限に改築や修繕ができるわけではありません。
建築基準法の規定の適用を受けない建築物(四号)については、政令第137条の2(構造耐力関係)によって、増築、改築、大規模修繕等の範囲が決められています。
たとえば、同条の第二号では、「増築に係る部分の床面積の合計が基準時の既存部分の床面積の2分の1以下」という条件が定められています。
つまり、再建築不可物件をリフォームする場合、工事は全体の2分の1以下に抑える必要があるのです。
建築業者に任せる際は、各種条例に適合したリフォーム内容となっているか否かを、書面やデータなどで確認させてもらいましょう。それらの資料をもとに、自ら役所で確認するくらいの用心が肝要です。
再建築不可物件を建築可能にする
再建築不可物件が再建築できないそもそもの発端は、接道義務に違反しているなど、現行の建築基準法に即していないためです。
つまり、建築基準法に沿うように敷地を整備すれば、再建築ができるようになる可能性が残されています。こちらでは、その具体的な方法について解説します。
・隣地を買取り、接道部分を拡大する
再建築不可物件の大半は、「敷地の前面道路と2m以上接する」という接道義務を満たしていないことが多いです。逆に言えば、そこさえクリアできれば、再建築が可能な土地に生まれ変わります。
たとえば、隣地を借りたり、買い取ったりすることで、間口を拡大したりなどです。隣地のうち、接道として必要な部分の名義変更をおこなえば、間口が拡大して接道義務を果たせます。
実際、弊社でもこの方法を用いることを前提に、土地を購入することもあります。
隣地の所有者との交渉に関しては、不動産会社に相談してみてください。個人間での取引に法的な問題はありませんが、手間がかかる上、トラブルにもなりやすい傾向があります。
また、少し話は逸れますが、「隣地を買い取る」という方法は、再建築不可物件を所有している人以外にも有効です。
たとえば、自分の土地(再建築不可ではない)の隣地が再建築不可物件である場合、隣地を安く購入することで敷地を拡大すれば、自分の土地の不動産価値を上げることにつながります。
隣地が再建築不可物件であるという人は、ぜひ参考にしてみてください。
・前面道路の幅員を広げる
接道義務に違反している要因が、「隣接する前面道路の幅員が4m未満である」ということなら、『セットバック』という方法で解決できる可能性があります。
セットバックとは、道路の幅員が4mになるように、敷地自体を後退させるという方法です。
たとえば、道路の幅員が1m足りないのであれば、敷地を1m後退させることで、元々敷地だった部分を「道路」とみなすことができます。こうした特殊な道路は「みなし道路」と呼ばれることもあります。
みなし道路は、見た目としては所有者の敷地に見えますが、建築基準法上は「道路」という扱いなので、塀や門、物置などの建造物を建てることはできません。
こうした工夫によって接道義務を果たし、再建築不可物件でなくなれば、不動産としての価値が上がるため、売却もしやすくなるでしょう。
・接道義務を免除してもらう
建築基準法第43条1項の但し書きによれば、建物自体に法的問題がなく、土地の安全性を行政から認められる場合に限り、接道義務が免除になる場合もあるとされています。
厳密には、同法で以下のように定められています。
- 敷地の周囲に広い空地がある
- 特定行政庁(地方自治体)が交通上・安全上・防火及び衛生上支障がないと認める
- 建築審査会の許可がある
接道義務を満たせない状況だとしても、上記の条件に該当する可能性があるのであれば、
建築審査会に免除の申請をしてみてもいいでしょう。
あくまでも例外的な措置なので、自治体によって基準は違いますが、うまくいけば接道義務が免除される可能性があります。
不動産で悩みを抱えている方は近畿住宅流通へ
土地活用を成功させるための近道は、1人で抱え込まず、積極的に専門家の意見を取り入れることです。
実際に取り組んでみるとわかりますが、土地活用には不動産の知識のほか、法律や条例に関する知識、マーケティングや経営など、広範囲に及ぶ知識やスキルが必要となります。
再建築不可物件のようにイレギュラーなものに関しては、一歩間違えると条例や法律に抵触してしまう可能性もあるのです。
その土地を使って実現できる活用方法の中から、最適な選択肢を選び、収益を得られる段階まで到達するのは容易ではありません。経営者として、何がベストな選択なのか判断に迷う局面にも出くわすでしょう。
だからこそ、土地活用で何か困ったら、弊社のような土地活用の専門家に相談してみてください。
弊社は昭和60年の創業以来、北は北海道から南は沖縄まで、数多くの土地活用に取り組んできました。その経験と知識、ノウハウを総動員して、最適な提案をさせていただきます。どうぞお気軽に近畿住宅流通までお問い合わせください。