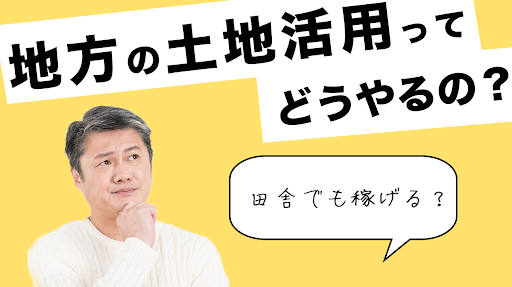地方の土地を有効に活用することは、多くの人にとって難しい課題です。人口が少なく、特殊な地形を持つ地域では、一般的な土地活用の方法が通用しないことも多々あります。
しかし、そんな土地でも適切な方法を選べば、収益を生み出すことは可能です。本記事では、田舎の土地で収益を得るための活用方法や注意点を解説します。地方の土地を有効に活用したい方は、ぜひ参考にしてください。
地方で土地を活用するのが難しい理由

地方でおこなう土地活用は、都心とは勝手が異なります。
人口が少なかったり、特殊な土地であったりすることが多く、活用にも創意工夫が必要なのです。そこでこちらでは、地方で土地を活用するのが難しい理由について、
- 地方の人口事情
- 地方の土地の傾向
の2点を解説していきます。
地方だと人口が少ないので、集客が難しい
土地活用の中でも代表的なものが「アパート・マンション経営」や「駐車場経営」ですが、地方では強くオススメできない理由があります。
そもそも人口が少なかったり、人口が減少傾向にあったりするため、賃貸需要が少ないのです。
また、高齢化や過疎化が進む地域では、テナントの賃貸需要も少ないです。資本力があり全国でチェーン展開する企業でさえ、出店を足踏みする傾向があります。
現に、全国展開しているコーヒーショップのスターバックスは、2015年に至るまで、国内で最も人口が少ない鳥取県に店舗展開をしていませんでした。
このように、企業の店舗開発の候補に入らなければ、テナントを誘致することも難しくなるため、「テナント向けの土地貸し」という活用も危うくなってくるのです。
とくに「限界集落」では、都会で当たり前のようにできる活用方法が困難となります。
限界集落とは、地方の中でも高齢者世帯がとくに集中しているエリアのことです。具体的には、65歳以上の人口が地域全体の半数以上を占めている状態を言います。
限界集落では、病院や物流などの必要最低限のインフラ環境すら整っていないこともあり、
土地活用をおこなうハードルは、都会よりもはるかに高くなるのです。
ちなみに、国土交通省の「過疎地域現状調査」によると、エリアごとの限界集落の割合は以下のようになっています。
高齢者が50%~100%未満の集落 高齢者が100%の集落 北海道 17.80% 0.60% 東北圏 11% 0.60% 首都圏 15.90% 0.60% 北陸圏 27.30% 1.90% 中部圏 26.10% 1.10% 近畿圏 23.20% 1.20% 中国圏 28.70% 1.70% 四国圏 31.50% 2.30% 九州圏 19.70% 2.30% 沖縄圏 2.50% 0 全体 21.30% 1.10%
引用:「平成27年度過疎地域現状調査」(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/common/001145930.pdf
こちらを見る限りでは、北陸圏、中部圏、近畿圏、中国圏、四国圏あたりが、とくに限界集落の数が多いようです。
このように、限界集落が存在する地域やそもそも人口が少ない地域では、土地活用の選択肢はかなり狭まると思っておいた方がいいでしょう。
田舎は特殊な地形の土地が多い

田舎では、特殊な土地が多い傾向にあります。
地形が特殊だと、建物を建てにくかったり、土地を整備する必要があったりして、活用が一筋縄ではいかないのです。
以下、田舎で見られる土地の特徴についてまとめたので、参考にしてみてください。
・変形地
変形地とは、ありがちな正方形や長方形の土地と違い、三角形や五角形の土地・高低差が激しい土地・細長い土地など、いびつな形状の土地のことを指します。
あまりに特殊な場合、「規格外」としてハウスメーカーの住宅が建てられなかったり、設計・建築コストが高額になったりすることもあるのです。
そのため、活用の不便さから、売却時に相場より安い価格に設定されることがあります。
一方、駐車場や資材置き場などであれば、住宅のように精密に設計された建物ではないので、変形地でも始めることが可能です。ただし、駐車場や資材置き場の適性があるかどうかは、立地や需要次第となります。
・狭小地(きょうしょうち)
狭小地とは、文字通り狭くて小さい土地のことです。明確な敷地面積の定義はないですが、20坪以下の土地は大抵狭小地と呼ばれます。
狭小地に向いているのは、看板広告や自動販売機などの運営です。初期投資も少なく、管理の手間もほとんどありません。
看板は契約相手である借り手が用意してくれますし、自動販売機の購入・設置はメーカーが負担してくれます。このように、狭い土地でもそれなりに活用の選択肢はあるのです。
ただ一方で、売却には不利な傾向があります。活用方法がかなり限られるため、買い手がつきにくいのです。
隣地の土地オーナーであれば、自身の土地を拡大できるという利点があるので、狭小地を買い取ってくれる可能性はあるかもしれません。
・傾斜地
傾斜地とは、文字通り傾斜がある土地のことで、「変形地」と同義で扱われることもあります。
変形地と同様に、建物を建てるには土地の整備や造成工事が必要なため、コストは高くなることが多いです。
また、平坦な土地と比べて価格が安くなる傾向があり、日当たりや見晴らしが良いことから、まれに住宅を建てる場所として好まれるケースもあります。
ちなみに、すでに造成工事が済んでいる土地の場合、平成18年の改正宅地造成法施行以前におこなわれた工事であれば、現行の基準に違反している可能性もあるので注意してください。
・旗竿地(はたざおち)
旗竿地は、土地の形状が旗と旗竿に見えることからそう呼ばれており、「路地状敷地(ろじじょうしきち)」とも呼ばれています。
具体的には、道路に面している土地が細長い道のようになっていて、その道の先に四角い土地があるという形状です。なお、旗竿地には「接道義務」があるため、敷地のうち2m以上は道路に接していなければいけません。
旗竿地のデメリットは、奥にある広がった土地が道路から見えにくいという点です。そのため、小売店や飲食店を営むには不向きと言えます。
ただし、旗竿部分の幅次第では、車の出し入れが可能なこともあり、そのような場合は戸建やアパート、駐車場がつくられるケースもあります。
・山林
山林は、敷地が広いのが長所ですが、草木が生い茂っているため、伐採や造成工事にコストがかかるのが短所です。
伐採した木々を売ることもできなくはないですが、伐採や運搬などの経費がかさみがちであり、大きな利益は期待できません。
また、敷地が広いので、日当たりが良い場所であれば「太陽光発電」が向いています。
ただし、電線の引き込み工事や電柱の設置、高圧線への変換工事など、やはり諸経費がかかります。さらに、山林で太陽光発電を始めてしまうと、地目が「山林」から「雑種地」という扱いに変わるため、固定資産税額が高くなってしまうのです。
総じて山林は、地方にある土地の中でも難易度の高い部類と言えるでしょう。
田舎の土地で稼ぐには?どの活用方法がおおすすめ?

こちらでは、地方のにある土地(田舎)で稼ぎたい方のために、オススメの活用方法を4つ紹介します。
土地貸し
オーナー自身は建物を建てずに、土地のみを貸すという活用方法が「土地貸し」です。「借地事業」と呼ばれることもあります。
収入源は「地代」だけですので、建物を賃貸で貸し出す場合と比べて収入は低くなってしまいます。
人口が少なく経済的規模が小さい田舎では、建物を建てて活用すること自体がリスクですので、土地だけでも借りたい人がいるのであれば、検討する価値はあるでしょう。
以下、土地貸しをおこなう際に知っておいて欲しい「事業用定期借地権」について解説します。
・事業用定期借地権とは
事業用定期借地権とは、事業用に土地を利用することのみを目的として、土地を借りられる権利のことを言います。貸主であるオーナーは土地のみを貸し、借主が土地の上に事業用の建物を建てるのです。
一般的に、土地貸しの契約を交わす時は、この権利を元に「事業用定期借地契約」が結ばれます。
この契約では更新がおこなわれず、期間満了時に建物を買い取る必要もありません。期間満了後、土地は更地の状態で返還されることになっています。
また、事業用定期借地権において重要なポイントは、2008年に法律が改正されている点です。
事業用定期借地権は「借地借家法」という法律で定められているのですが、2008年までは契約期間が「10年以上、20年未満」とされていました。
しかし、借主側としても借金をして建物を建てるわけですから、借金を返済しつつ収益を上げるには、少々タイムリミットが短かったのです。そのため、借主としては、解体しやすく耐用年数の短い建物でないと採算が合いませんでした。
そのような状況を受けて、現在では契約期間が「10年以上、50年未満」に変更されているのです。
以下、事業用定期借地権のメリットとデメリットを紹介しますので、土地貸しを検討している方は参考にしてみてください。
【事業用定期借地権のメリット】
事業用定期借地権の一番のメリットは、「リスクが小さく、長期間にわたって収益が安定しやすい」点です。
契約期間は10年以上、50年未満と長く、資本力のあるテナントと契約できれば、長期間安定して賃料を得続けることができます。
期間満了後には、更新もなく更地の状態で返還されるため、次の活用プランも余裕を持って考えることができるのです。
・「土地を活用したいが、建物を建てるリスクは負えない」オーナー
・「建物を建てるのはいいが、土地を購入するリスクは負えない」テナント
両者の利害がちょうど一致した活用方法といえるでしょう。
【事業用定期借地権のデメリット】
デメリットは、まず「契約相手が1社に絞られてしまう」という点です。
アパート・マンション、オフィスビルや商用施設の場合は、複数の借主と契約ができるため、空室リスクを分散できます。
その点、事業用定期借地権の場合は、基本的に1社に土地を貸しだすので、リスクの分散ができません。
万が一、借主の事業が上手くいかなければ賃料支払いが遅延したり、期間満了前に退去される可能性もあるのです。最悪の場合、夜逃げでもされてしまったら、建物の解体費用や撤去費用をオーナー自身が負担せざるを得なくなります。
もう1つのデメリットが「契約面でのトラブル」です。
契約相手によっては、一部の費用を貸し手が負担することを条件に、借地契約を結ぶといったケースもあります。
その場合、土地の管理費用や建物の修繕費用、電気、水道、ガスなどのインフラ環境の整備費用など、契約時に細かく分担を決めておく必要があるのです。
資材置き場
ある程度の広い敷地であれば、資材置き場として貸し出すという方法もあります。
実際、資材や機材を扱うことが多い建築会社や解体会社は、田舎を拠点としていることが少なくありません。建物を建てる必要がないため、初期費用もほぼかからず、法律や条例の規制を受けることも少ないので、気軽に始めることができます。
また、土地の形状や広さ、日当たりなども関係なく、基本的にどのような土地でも実現可能です。さらに、整地作業もいらず、更地に戻すのも簡単ですので、土地活用未経験の方にとってハードルが低い活用方法と言えます。
ただし、都合よく資材置き場を探している企業を見つけられるかは話が別です。不動産会社に仲介の協力を仰ぐなど、努力が必要でしょう。
また、資材置き場は騒音がつきものであり、粉塵が巻き上がる可能性もあります。近隣の住宅地がある場合は、それがトラブルに発展することもあるので注意が必要です。
最大のデメリットとしては、「収益性が低い」ということです。資材置き場は基本的に賃料が低いため、固定資産税分の利益が出れば御の字でしょう。
いずれにしても、暫定的な活用の選択肢として資材置き場は有効ですし、建物を借りる需要も借地の需要もない場合は、オススメの活用方法と言えます。
貸し農園
貸し農園とは、農業を楽しみたい個人向けに、作物や植物を育てるための農地を貸し出すという活用方法です。
日常的に農業と触れる機会のない都会在住の人や、マンションに住んでいて庭がない人などから需要があります。
「レンタル農園」や「シェア農園」、「体験農園」などと呼ばれることもあり、契約者1人につき、数千円〜1万円程度の賃料を得ることができます。
以下、
・貸し農園のメリット、デメリット
・混同されがちな「貸し農園」と「市民農園」との違い
について解説しますので、参考にしてください。
【貸し農園のメリット】
農地さえあれば、初期投資をせずにすぐ始められるのがメリットです。
建物の建設工事が必要ないという点では、駐車場や太陽光発電も同じですが、それらは土地の舗装工事やソーラーパネルの設置工事が必要となります。その点、貸し農園は特別な設備の導入や工事が必要ないため、圧倒的に初期費用が少ないのです。
【貸し農園のデメリット】
デメリットは、「収益性の低さ」と「税金の軽減措置がないこと」です。
建物内で人が暮らしたり、事業をおこなわれたりするわけではないので、必然的に賃料は低くなります。また、雪が降る地域では冬に農作業ができないため、休業せざるをえないでしょう。
賃料が低い上に稼働できる期間も限られるため、収益性を重視する方にはあまりオススメできません。
さらに、「税金の軽減措置がない」という点もデメリットです。農地として活用しても、固定資産税や相続税などの負担は変わらないため、節税対策をしたい人には向いていない活用方法と言えます。
【「貸し農園」と「市民農園」の違い】
補足までに、よく混同されがちな「市民農園」との違いについて説明しておきます。以下が比較表となりますので、農園として活用を検討している方は参考にしてください。
| 貸し農園 | 市民農園 | |
| 開発者 | 農家もしくは企業 | 区市町村、農業協同組合など |
| 利用料金 | 高め | 低め |
| 入会金・運営費 | 取ることができる | 一般的に取らない |
| 指導員 | 必要 | 不在のこともある |
運営者によってサービスの詳細が異なるため、一概には言えませんが、あくまで一般的な認識として上記のような違いがあります。
2.4 売却も視野に入れる
適切な活用方法が見つからなかったり、自分で活用するのが困難だったりする場合は、「売却」を検討しましょう。
土地を相続したのであれば、相続税の申告期限(相続を知った日から10ヶ月)がありますので、あとあと焦って売却しないよう、早めに動き始めることをオススメします。
しかし、そうは言っても地方の土地は簡単には売れません。そもそも活用方法に困って売ろうとしている土地ですから、中々買い手が見つからないのです。
そこでこちらでは、地方の土地を売却する上で有効な方法を3つ紹介します。
【方法1:仲介会社を通じて売却する】
不動産の仲介会社を通して、買い手を探してもらうのが最もベーシックな方法です。
土地を不動産会社に査定をしてもらい、「一般媒介契約」を結びます。一般媒介契約とは、複数の不動産会社に対して仲介を依頼する契約形態です。
複数の仲介会社が一斉に土地を売りに出せば、露出が増えるため、買い手候補の目に留まって売却できる可能性が高まります。仲介会社としても、他の競合より早く買い手を見つける動機ができるので、売り手としては好都合な方法なのです。
一般的には3ヶ月〜半年程度で買い手候補が見つかりますが、地方にある土地はそれ以上の時間がかかるケースもあります。
参考までに、売買が成立した際の仲介料は、一般的に以下のようになっています。
| 取引額 | 仲介料の割合 |
| 200万円以下部分 | 取引額の5%+消費税以下 |
| 200万円超え、400万円以下 | 取引額の4%+消費税以下 |
| 400万円超え | 取引額の3%+消費税以下 |
補足として、もし土地が「市街化調整区域」(市街化を抑制する地域)にあるのなら、市街化調整区域での取引経験が多い不動産会社や訳あり物件を得意とする不動産会社を探しましょう。
市街化調整区域は、住宅ローンが通りにくかったり、建築物に対する規制が厳しかったりなど、何かと売りにくい土地だからです。現地調査などの手間もかかり、経費がかさむため、仲介会社としても利益を出しにくいと言われています。
そこで、市街化調整区域に強い仲介会社であれば、売買実績やノウハウがありますし、売買が困難な場合の対処法についても相談に乗ってくれるでしょう。
【方法2:不動産会社に買い取ってもらう】
不動産会社自身が直接土地を購入してくれるケースもあります。買い取ってもらう方法は主に2つです。
1つ目は「即時買取」で、ある程度資本力のある会社であれば、最短1週間、長くて1ヶ月前後で買い取ってもらえます。
1日でも早く売りたい人に向いている方法ですが、スピードを重視する分、価格は相場よりも少々安くなるのが難点です。
もう1つの方法が「買取保証」です。
買取保証とは、「一定期間のうちに売却に至らなかった際、不動産会社が買い取る」という契約となります。
一定期間、不動産会社が販売活動をおこないますが、最終的に売買契約を締結できなかった場合、事前に決めた価格で不動産会社が買い取るのです。
買い手が見つかり、売買契約に至った場合は仲介手数料が発生しますが、契約が不成立となり、不動産会社が買い取る場合は手数料が発生しません。
【方法3:個人間で売却する】
法律上、個人間で不動産を売買することは可能です。
不動産会社を介したときに発生する仲介手数料が発生しないため、金銭的なメリットは大きいと言えます。
しかし、不動産の個人間による売買はデメリットも大きいです。
まず、売買契約書や重要事項説明書などの資料を作成する手間がかかります。仮にそれらの資料作成ができたとしても、新たな問題が発生するのです。
買い手がローンによる購入を検討している場合、金融機関では宅地建物取引士の記名や押印がない資料は、正式書類として受理されない可能性が高いです。
金融機関としても、契約書の不備によるトラブルや、契約者同士の結託によるローンの不正利用を避けたいので、ローン審査の基準を厳しくせざるを得ないのです。
個人間で売買をおこなう際は、このようなリスクがあることを知っておきましょう。
リスクを承知の上で、それでも個人間で売買をするのであれば、オーナー自身が積極的に販売活動をする必要があります。
近隣住民への周知はもちろんのこと、人が集まりやすい場所に顔を出して、人脈を築く努力も必要です。
ちなみに、近年は新型コロナウィルス感染症の影響で、都会で暮らす人々の生活意識や行動に変化が起き始めています。
内閣府が令和2年におこなった調査によると、東京圏在住で地方移住に関心がある人の割合は「全体の3割弱」でした。人口密度の低い田舎に移り住みたい人が増えており、とくに20代は「37.9%」と高い数値となっています。(※1)
「都会から田舎に移住したい」という需要は高まりつつあるので、接点さえできれば、個人間で売買できる可能性もゼロではないでしょう。
※1:「新型コロナウイルス感染症の影響下における 生活意識・行動の変化に関する調査」(内閣府)https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/covid/pdf/result2_covid.pdf
田舎の広い敷地なら、キャンプ場やサバイバルゲームの施設もオススメ

田舎特有の広い敷地や山林の地形を活かして、キャンプ場やサバイバルゲームの施設を運営するという方法もあります。
以下、具体的に活用方法を解説しますので参考にしてください。
キャンプ場
田舎にあるような、自然豊かで広々とした土地に向いているのが「キャンプ場」です。
ソーシャルディスタンスを保ちながら、アウトドアを楽しめる娯楽として、近年ブームが再燃しています。
キャンプ場と一言に言っても、そのスタイルは様々です。宿泊施設や焼き場が完備されている施設もあれば、オートキャンプのように利用者が自身で火を起こしたり、テントを建てるケースもあります。
どのような形態のキャンプ場にするかによって、適用される法律や自治体への許可・届出の内容が異なるため、以下順番に説明していきます。
・林地開発について
まず、基本的に森林を伐採するには、自用地であったとしても自治体の長による許可が必要です。
具体的には伐採・伐採後の造林の届出、小規模林地開発届、造林報告届などです。また、1ヘクタール以上の広さの森林を伐採するには、知事の許可が必要となります。
・建築物について
宿泊施設や管理棟などの、人が寝泊まりする建物を建てる際は、自治体の「建築確認」が必要なことがあります。
少なくとも、都市計画区域内にある土地では必ず建築確認が必要です。建築物には、建築基準法や都市計画法など、複数の法律が絡んでくるため、設計段階に入る前に十分に確認するようにしましょう。
・旅館業営業許可について
利用者の宿泊施設がある場合は、旅館業営業許可が必要です。
・飲食店業の許可
食材を販売・提供する場合には飲食店業の許可が必要です。
・消防署への届出
バーベキュー用の火を起こす設備がある場合は、消防署に対して「防火対象物使用開始届」を届け出なければなりません。利用者自身が火起こしや調理をするための「焼き場」は、対象とはなりません。
・酒類販売業免許について
酒類を販売・提供する場合は、酒類販売業免許が必要です。コップやグラスにアルコールを注いで出す場合は、さらに飲食店営業許可も必要となります。
サバイバルゲーム場
田舎の山林の活用方法として、近年注目を浴びているのが「サバイバルゲーム場」です。
サバイバルゲームとは、戦場を模した場所でエアガンなどを打ち合い、勝敗を決める遊びのことを言います。サッカーやバスケットのように長方形のコート上でおこなわれるものではなく、山林の地形を活かした広いフィールドでおこなわれるものです。
1度に数十人が利用する場所ですので、利用者用のトイレやスタッフ用の事務所など、最低限の設備は必要となります。
サバイバルゲーム場特有の配慮も必要です。まず、利用者が誤って隣地との境界線を超えてしまわないよう、区画をしっかり定めておかなければいけません。
また、利用者がエアガンで打った弾が隣地に入る危険もありますから、区画を覆うようにバリケードを設置するなどの工夫も必要です。
さらに、山林の中で人が自由に動き回るためには、最低限の木々の伐採、野生動物への対策なども欠かせません。
このように細かな配慮は必要ですが、同じ山林を活用したキャンプ場と比べれば、初期投資は比較的少ないでしょう。
ただし、サバイバルゲーム場の歴史事態がまだ浅いため、活用上の法規制が曖昧な部分が多いです。ゲーム場としての活用が可能かどうか、年齢制限をしたほうがいいかなど、必ず自治体へ相談するようにしてください。
地方の土地を活用する際の注意点

最後に、地方の土地を活用する際の注意点について解説します。
住宅の賃貸需要が低い
繰り返しになってしまいますが、住宅の賃貸需要が低いことは、土地活用をおこなう上で大きなハンデとなります。
そもそも人口が少ないという事情もありますが、都会と違って企業や大学などが少ないため、「アパート・マンションから通う」という習慣自体が乏しいのです。
バスや電車の便数も少なく、通うには不便なことが多いため、需要があるとしても駅近、学校施設や工場近辺などの限られたエリアとなります。
そのような状況で、借金をしてまで建物を建てるのは、かなりリスクが高いです。よほどの確信を持てない限り、住宅賃貸経営は避けた方がいいでしょう。
地域によって規制があるので注意する
原則として、土地活用をおこなう際は、都市計画法に則った活用をしなければなりません。具体的には、該当する区域のルールを守って活用する必要があるのです。
都市計画法において、国土はすべて以下の5つの区域に分類されています。
・市街化区域
住宅や店舗などを積極的に建てる地域です。
・市街化調整区域
自然環境の保護が目的の地域であり、住宅や店舗、商用施設を建てられないことも多いです。建物を建築するには、基本的に都道府県知事の許可が必要となります。
・非線引都市計画区域
市街化区域と市街化調整区域以外の地域を指します。
・準都市計画区域
都市計画区域ではないエリアで、積極的な開発をよしとしない地域です。
・都市計画区域外
都市計画法に含まれていない地域です。
基本的には都会であるほど土地の開発に関する規制は厳しく、田舎であるほど規制は緩くなる傾向があります。
なお、地方の土地は「非線引都市計画区域」や「都市計画区域外」であることが多いです。
それらの区域では、都会の土地活用でありがちな集団規定(接道義務や容積率など)が適用されず、建築物への規制(都市計画法によるもの)もほとんどありません。
その代わり、農地であれば農地法が適用されますし、山林であれば宅地造成等規制法などが適用され、都会とはまた別の規制を受けることになるのです。
農地を転用して別の活用をするという選択肢もありますが、区域によっては転用が難しいケースもあります。
このように、都市計画法の規制が緩い地方の土地であっても、活用には何かしらの規制が存在します。事前に自治体の窓口に確認するなどして、慎重に取り組みましょう。
整地の費用がかかることもある
地方の土地の中には、長期間十分な管理がされず、草木が生い茂っていることも珍しくありません。そういった土地を活用するには、伐採や抜根などの整地作業が必要となります。
整地費用の相場は1㎡当たりおよそ300円~600円ですが、あくまでこれは特別な工事が必要ない場合です。
地中に埋設物があったり、敷地内に廃棄物があったりする場合は別途費用が発生します。ちなみに抜根は、木1本につき5000円前後が相場です。
また、傾斜の激しい土地での整地作業は業者の技術力が必要であり、1㎡あたりの単価も2倍〜4倍に上がることもあります。
土地の形状や荒れ方次第では、整地をするだけでも相応の費用がかかるということを覚えておきましょう。
地方の土地活用に悩んだらプロに相談する
過去に土地活用の経験がないのであれば、できるだけプロに相談することをオススメします。
とくに地方の土地は、立地や地形次第で活用方法がかなり制限されるため、土地活用未経験者の方が取り組むには、かなりハードルが高いからです。
相談する前に、できるだけ測量を済ませておく
活用方法が決まっておらず、どのような活用ができるかリサーチ中の人は、まず所有している土地について理解を深めましょう。
一番確実な方法は、土地家屋調査士に「測量」をしてもらうことです。測量によって、土地・建物・塀などのおおよその面積や高さ、寸法がわかります。
それらの情報をまとめた「測量図」があれば、今後どこに相談に行くにしても、話がスムーズに進みやすくなるでしょう。
費用としては、簡易的な「現況測量」だと10万円〜20万円、官公署を介した「境界確定測量」だと60万円〜80万円ほどかかります。
それなりにコストはかかってしまいますが、土地を活用して事業をするにしても、売却するにしても、測量を済ませておくと何かと都合が良いです。
例えば、敷地面積は土地の取引価格を決める際の重要な指標となります。
土地の販売活動をする中で、面積に誤差が発覚すれば、取引価格の信憑性が下がってしまいます。買い手の不信感を煽ってしまうのです。
また、土地の上に何か建物を建てる場合も、土地の面積は重要な要素となります。些細な面積の誤差によって、建築設計に大幅な変更をくわえなければならないこともあるのです。
先述のように、地方の土地は変形地や傾斜地であることが珍しくないので、なおさら正確な情報が求められます。
境界確定測量であれば、隣地オーナーの立ち会いのもとで境界を明確にできるので、活用時のトラブル防止にもつながります。
地方の土地活用の相談先は、相談内容によって異なる
土地活用の相談先は、相談内容によって異なります。以下、相談内容ごとに相談先の候補をまとめたので、参考にしてください。
| 相談内容 | 相談先 |
| ライフプランについて (所有し続けるか、売却か) |
ファイナンシャルプランナー |
| 売却について | 売買実績の豊富な地元の不動産会社 |
| 融資について | 金融機関 |
| 建築確認について | 都道府県または市町村の建築主事(※) |
| 建築物について | 工務店、住宅メーカー |
| 節税について | 土地活用に詳しい税理士 |
| 名義変更や転用について | 司法書士 |
| 土地活用全般 | 専門業者、コンサルタント |
(※)建築基準法の規定により、建築確認をおこなうために地方公共団体に置かれた公務員
土地活用で悩んだら近畿住宅流通へ
繰り返しになりますが、地方の土地は都会と比べて、非常に扱いにくいものです。
都市計画法による規制は緩い(もしくはない)ものの、適用される法律は土地ごとに異なり、用途はかなり限定的となります。
「土地を相続しただけで、不動産や法律のことには詳しくない」という方にとっては、かなり難易度が高いでしょう。自己流で活用して損失を被ってしまわぬよう、ぜひ土地活用に詳しいプロに相談みてください。
もし、身近に相談できる方がいないのであれば、弊社が力になります。
賃貸住宅、オフィスビル、医療モール、宿泊施設、借地事業など、全国各地で土地活用に取り組んできた弊社だからこそ、伝えられる情報やノウハウがあります。ぜひ、お気軽に近畿住宅流通までお問い合わせください。