「更地を相続したけど、どう活用すべきかわからない」
「ずっと放置している更地を使って、何かビジネスができないだろうか?」
今回は、このような悩みを抱える土地オーナーの方向けに、
・更地を放置し続けるデメリット
・オススメの活用方法、
・更地を活用する上での注意点
などをお伝えしていきます。ぜひ参考にしてみてください。
更地をそのままにしておくデメリット

「更地」とは、土地の上に建物や工作物がなく、借地権などの第三者の利用権利がない状態の土地を指します。
「空き地」と混同されることが多いですが、空き地は権利関係と関係なく、事実上使用されていない状態の土地のことです。小屋や工作物が放置されていれば、それは「更地」ではなく「空き地」ということになります。
つまり、権利関係によるしがらみや土地の上に不要な物がない「更地」のほうが、土地活用をするにはオススメなのです。
では、そのような更地を活用せずに放置すると、具体的にどのようなデメリットがあるのか解説していきます。
固定資産税や都市計画税が高くなる
更地を放置する最大のデメリットは、固定資産税や都市計画税などの税負担が重くなるという点です。
では、更地の状態と住宅がある状態とで、課税標準額(税額計算の基礎となる金額)がどれくらい違うのか、比較した表が以下となります。
| 土地の種類 | 固定資産税の算出方法 |
| 更地 | 課税標準額×1.4% |
| 小規模住宅用地 (敷地面積200㎡まで) |
課税標準額×1/6×1.4% |
| 一般住宅用地 (敷地面積200㎡以上) |
課税標準額×1/3×1.4% |
このように、住宅を建てた場合と比べて、更地の固定資産税の課税標準額は「3倍、または6倍」となります。
固定資産税ほどではないですが、都市計画税も住宅があるか否かで、課税標準額が大きく変わるのです。以下がその比較表となります。
| 土地の種類 | 都市計画税の算出方法 |
| 更地 | 課税標準額×0.3% |
| 小規模住宅用地 (敷地面積200㎡まで) |
課税標準額×1/3×0.3% |
| 一般住宅用地 (敷地面積200㎡以上) |
課税標準額×2/3×0.3% |
住宅を建てた場合と比べて、更地の固定資産税の課税標準額は「1.5倍、または3倍」となります。
古いアパートや一軒家の中には、入居者を募集していないのに、建物を解体せず放置しているケースがあります。しかし、それは更地にすると固定費が一気に上がってしまうからという理由から放置をしているのです。
相続税が高くなる
更地のままにしておくと損をするのは、固定資産税や都市計画税だけではありません。
「相続税」も高くなります。
例によって、建物を建てることで相続税の負担を軽減できる場合があります。
相続税の軽減措置には、主に「小規模宅地の特例」と「貸家建付地」の2つがあるので、順番に説明していきます。節税を考えている人は、ぜひ参考にしてください。
・小規模宅地の特例
小規模宅地の特例は、不動産や事業を相続人に円滑に承継するために設けられた制度です。
相続税は現金による一括納付が原則なので、現金に余裕がなければ、相続税を支払うために相続した土地を売却せざるを得なくなります。せっかく相続した土地を失うことは、残された遺族にとって好ましい状況とは言えないでしょう。
特例措置は、そのような状況を避けるために設けられています。では、小規模宅地とは具体的に以下のように定義されています。
特定居住用宅地等…自宅が建っている土地
特定事業用宅地等…自営業の店舗や工場などが建っている事業用の土地
相続以前に被相続人が営んでいた事業を、親族が承継することが条件
貸付事業用宅地等…不動産賃貸業や駐車場を営む土地
相続以前に被相続人が営んでいた事業を、親族が承継することが条件
これらに該当する土地は、相続税の軽減措置を受けることができるとされています。
それぞれ上限面積と減額割合が決められており、上限の範囲内で組み合わせて併用することが可能です。
以下、土地の利用区分ごとに、特例の対象となる上限面積と減額割合をまとめた表となるので、参考にしてください。
| 【小規模宅地等の特例の内容】 | ||
| 利用区分 | 上限面積 | 減額割合 |
| 特定居住用宅地等 | 330m2 | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400m2 | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200m2 | 50% |
このように、土地の利用区分によっては最大で80%の減額となるため、節税効果はかなり大きいといえます。
・貸家建付地
もう1つの軽減措置が「貸家建付地」に該当する場合です。貸家建付地とは、土地の上に賃貸用の建物を建てて、第三者に貸している状態の土地を指します。
代表的なものが、アパート・マンション、貸家などです。以下が減額の計算式です。
自用地評価×{1-(借地権割合×借家権割合×賃貸割合)}
1つ1つの用語の解説は割愛しますが、簡単に言えば、「賃貸割合(入居率)によって上下するもの」という認識で問題ありません。
要するに、「ただ貸家をやっている」というだけではなく、修繕やリフォーム、積極的な入居者募集などによって、「満室を目指して精力的に経営しているか」が評価の基準となるのです。
賃貸割合が高いほど評価額が下がり、相続税の負担は軽くなります。
たとえば、自用地評価が3000万円の土地があったとして、借地権割合が50%、賃貸割合が90%のアパートを所有している場合、評価減の計算式は、
3000万円×{1-(0.5×0.3×0.9)}=2595万円
となります(借家権割合は全国一律で30%です)。
さらに、貸家建付地は前述の「貸付事業用宅地等」にあたるため、「小規模宅地の特例」との併用が可能です。
200㎡までの部分は50%の評価減となるので、上記の例に当てはめると、最終的な評価額は1297万5千円となります。
ただし、貸家建付地と小規模宅地の特例を併用する場合、
「相続税を申告するまえに、貸家建付地を相続する人間が確定していること」
「相続人が、相続税の申告期限までに貸家建付地を保有し続けていること」
「相続人が、相続税の申告期限までに不動産賃貸業を承継し、事業を継続していること」
の3つの要件を満たす必要があります。
維持していくのが大変
更地を活用せずに放置するデメリットは、税金面だけではありません。
誰も管理する人間がいなければ、無断で利用されて溜まり場となったり、駐車場として使われたり、ゴミを不法投棄される可能性もあります。
草木が生い茂って見栄えが悪くなれば、売却にも不利です。定期的な手入れをして、土地を管理する必要があるでしょう。更地を所有している限り、こういったリスクを抱えつづけることになります。
更地の土地活用アイデアを紹介

続いて、更地の活用アイデアを紹介していきます。それぞれメリットとデメリットも解説しますので、合わせて参考にしてみてください。
賃貸アパート・マンションの建築
土地活用の方法の中でも、最もイメージしやすいのが賃貸アパート・マンションかもしれません。更地にアパートやマンションを建てて、入居者を募集し、家賃収入を得るという方法です。
階数や戸数が多いほど、より多くの賃料を得ることができるため、効率的に土地を活用できます。
建物の建築から入居者の募集に至るまで、全面的にサポートしてくれる専門業者も存在するので、立地がよく、きちんとニーズに応えることができれば、毎月安定した収益を得られる可能性があるでしょう。
【メリット】
主なメリットは、
- 安定した収益を得やすい」
- 「建物の減価償却をおこなえる」
- 「損益通算ができる」
この3つです。
・安定した収益を得やすい
安定して収益を得られたとしても、利益として本格的に手元に残るのはローン完済後と思っておいたほうがいいでしょう。
一般的に、アパート・マンションは金融機関からのローンを利用して建てるため、賃貸事業開始十数年から数十年の間、毎月ローンの返済があります。
さらに、月々発生する共用部分の公共料金、臨時の修繕費用、管理会社への委託料、大規模なリノベーション、毎年支払う固定資産税や所得税など、意外と出費が多いのが賃貸アパート・マンション経営の特徴なのです。
中でも大きな支出がローン返済なので、返済が終わるまでは中々メリットを感じにくいかもしれません。
・建物の減価償却をおこなえる
2つ目のメリットが「建物の減価償却をおこなえる」という点です。
減価償却とは、長期間使用する固定資産を、使用期間に応じて分割しながら経費計上するということです。
たとえば、1億円のマンションを建てたとして、そのマンションの耐用年数が20年である場合、毎年500万円を20年かけて経費計上します。ポイントは、実際に手元からお金が出ていくわけではないのに、毎年一定の金額を経費として計上できるという点です。
つまり、賃貸業によって得られる利益を圧縮することができるため、不動産所得の所得税を節約することができます。
・損益通算ができる
3つ目のメリットが「損益通算」です。
会社員として働きながら不動産の賃貸業をすれば、会社員として得られる所得、賃貸業から得られる不動産所得、収入源が2つあることになります。これらの2つの所得を合算することを損益通算と言います。
たとえば、賃貸業が赤字だった時、損益通算によって本業の所得と賃貸業の赤字とを相殺することが可能です。それによってトータルの所得額が減り、所得税の節税につながりるというわけです。
損益通算に関する詳しい情報は、国税庁のホームページを確認してみてください。(※1)
・節税効果がある
前章で解説したように、更地に建物を建てると、固定資産税や都市計画税の節税効果があります。アパート・マンションがあるということは貸家建付地でもあるので、相続税の節税にもつながりますし、200㎡までの部分はさらに50%の評価減となるのです。
【デメリット】
一番のデメリットは、他の活用方法と比べて圧倒的に「初期費用の負担が大きい」ということです。
少なくとも数千万円、多くて億単位の初期投資が必要となるため、収支のシミュレーションやローンの返済計画を綿密におこなう必要があります。資金繰りに失敗すれば、最悪自己破産に追い込まれる可能性もあるのです。
立地が良くないのであれば、そもそも賃貸アパート・マンションには不向きなので、別の活用方法を検討した方がいいでしょう。
立地が良かったとしても、競合が多ければ、賃料の値下げ競争に陥る可能性もあります。
地域によっては、将来的に人口が減るところもあるでしょう。年々人口が減っていたり、空き家や空室が目立っている地域では、賃貸アパート・マンションの経営は避けることをオススメします。
※1:「損益通算」(国税庁)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm
新築戸建て賃貸の建築
一戸建ての住宅を建て、賃貸物件として経営するという方法もあります。戸建賃貸経営とは、一戸建ての住宅を賃貸物件として貸し出し、家賃収入を得るという活用方法です。
アパート・マンションと比べて戸数は少なくなりますが、しっかりニーズに応えられれば、安定した収益を得られる可能性があります。
【メリット】
主なメリットは、
- 立地が良くなくても、入居者がつく可能性が高い
- アパート・マンションと比べて初期費用
- 節税効果がある
この3つです。
・立地が良くなくても、入居者がつく可能性が高い
アパート・マンション経営の場合は、ある程度の敷地面積の広さ、立地の利便性、日当たりの良さなどが重要です。
しかし、戸建の賃貸経営の場合は、そこまで重視する必要がありません。
戸数が少ないため、極端に広い土地である必要はないですし、日常的に車を利用するファミリー層をターゲットにすれば、駅近である必要もないのです。敷地内に駐車場を設ければ、それで事足ります。
また、狭小地や変形地であっても、土地の特性に合わせて柔軟に設計・建築できるのも戸建の大きなメリットと言えます。
・アパート・マンションと比べて初期費用を抑えやすい
戸建はアパート・マンションと比べて建物の規模が小さいので、初期費用を抑えやすいです。
月々のローン返済額を抑えられるため、資金繰りが失敗するリスクも、アパート・マンションと比べて低くなります。
また、元金が少なければ、金利上昇によって返済額が急激に増えるリスクを抑えることもできます(変動金利でローンを組んだ場合に限り)。
・節税効果がある
アパート・マンションと同様に、更地に建物を建てると、固定資産税や都市計画税の節税につながります。
貸家建付地でもあるので、相続税の節税にもなり、200㎡までの部分はさらに50%の評価減となるのです。
自動車駐車場の経営
更地の活用方法として、自動車駐車場の経営もオススメです。他の活用方法と比較して初期投資も少なく、管理もそこまで手間ではありません。
選択肢としては、「月極駐車場」か「コインパーキング」の2つがあります。
月々固定の賃料を得るなら月極駐車場、時間貸しをして、利用時間ごとに賃料を得るならコインパーキングがいいでしょう。
どちらのスタイルが向いているかは、立地や土地周辺の環境によります。駐車場の設備がないアパート・マンションの近隣であれば、月極駐車場のニーズがあります。同様に駐車場がない、もしくは少ないオフィスビルや飲食店の近隣であれば、コインパーキングの需要があるといえるでしょう。
【メリット】
主なメリットは、
- 初期投資の負担が小さい
- 管理の負担が小さい
- 後々用途変更をしやすい
この3つです。
・初期投資の負担が小さい
貸家のように建物を建てるわけではないため、金融機関から巨額の融資を引く必要がありません。とくに月極駐車場の場合は、初期費用0円で始めることもできます。
コインパーキングの場合は0円とはいきませんが、それでも100万円以下の初期投資で十分実現可能です。
駐車場経営は、自己資本のみで始められる数少ない活用方法の1つと言えるでしょう。
・管理の負担が小さい
駐車場の管理は、アパート・マンションのような修繕工事や大規模なリノベーションがなく、管理の負担はかなり小さいと言えます。
管理業者を入れずにオーナー自身が管理するとしても、簡単な清掃や設備点検、トラブル対応、年1回の確定申告くらいでしょう。
もし専門業者に管理業務を委託するなら、オーナーの業務は基本的に確定申告のみです。委託料として固定費が増えてしまいますが、手離れの良さを重視したい方には向いているでしょう。
・後々用途変更をしやすい
月極駐車場でも、コインパーキングでも、基本的には更地と大差がないため、撤退時に解体作業も大きな負担とはなりません。後々活用の用途を変更する際も、スムーズに転用ができます。
【デメリット】
主なデメリットとしては、
- 高い収益を狙いにくい
- 節税効果を期待できない
この2つです。
・高い収益を狙いにくい
駐車場経営は、参入しやすいメリットと引き換えに、高い収益を狙いにくいというデメリットがあります。
管理業者を入れずにオーナー自身が駐車場を運営すれば、利益を最大化できますが、月極駐車場の場合はそもそも駐車台数に限度があるので、どれだけ頑張っても売上の最大値は変わりません。
コインパーキングであれば、売上の上限はもっと伸びる余地がありますが、設備投資が必要なので初期投資の負担が増えてしまいます。
また、一般的にはコインパーキングの運営はオーナー自身がやるというより、専門業者に土地を一括借り上げしてもらい、運営を委託するオーナーが多いです。
一括借り上げの場合は、月々の賃料が固定となり金額も高くないため、やはり収益性は低くなってしまいます。
・節税効果を期待できない
土地活用をおこなう方の中には、節税目的で始める方も少なくありません。確かに、貸家、アパート・マンションであれば、固定資産税や都市計画税、相続税の節税効果を期待できますが、駐車場経営は同様の効果を期待できないのです。
その理由は、駐車場が基本的に「更地」と同様の扱いとなっているからです。
土地の上に建物があるわけではないので、「住宅用地」や「貸家建付地」のように税金の優遇措置を受けられないのです。
ただし、やり方次第では、駐車場経営で節税対策をすることもできます。
きちんとアスファルト舗装された駐車場であれば、「貸付事業用宅地」とみなされ、敷地面積200㎡までは相続税評価を50%減額できるのです。
駐車場経営はそもそも節税に向いている活用方法ではありませんが、相続することを前提に活用するのであれば、有効な施策と言えます。
土地貸し
土地貸しとは、第三者に土地を貸し出して賃料を得る活用方法です。
オーナー側が何か建物を建てたり、初期投資をする必要はありません。資本に余裕のある企業に貸すことができれば、10年、20年と安定して賃料を得続けることができます。
ちなみに、第三者が土地代を払うことで、土地を借りられる権利を「借地権」と言います。
借地権には複数の種類があり、それぞれ利用目的や契約期間、契約形式が異なるのです。
詳しくはこちらの記事を参考にしてみてください。
トチカツプロ/土地活用の借地権について|メリットとデメリットについて解説
https://kinki-jr.com/tochikatsu-pro/land_utilization_lease/
【メリット】
主なメリットとしては、
- 長期的に安定した賃料を期待できる
- 節税効果を期待できる
この2つです。
・長期的に安定した賃料を期待できる
コンビニやドラッグストア、飲食チェーン店や家族葬など、土地貸しでは立地を活かして長期的に土地を借りてもらえるケースが多いです。
そのため、10年、20年単位で長期的に安定した賃料を得られる可能性があります。
・節税効果を期待できる
事業用の土地貸しであれば、特に相続税の軽減が期待でき、節税面でのメリットは大きいと言えます。定期借地権が設定されている土地であれば、一定の相続税評価額減が期待できます。
【デメリット】
主なデメリットとしては、
- 長期間利用が制限される
- 高い収益性を期待できない
この2つです。
・長期間利用が制限される
土地貸しは10年、20年と長期間の契約が一般的であるため、その間オーナーは自由に自分の土地を利用できなくなります。
契約期間中はオーナーの都合で一方的に契約を解除したり、用途変更や売却をしたりできないので、土地貸しをする場合は長期で活用することを前提に、慎重に契約相手を選びましょう。
・高い収益性を期待できない
土地貸しは、建物を貸す場合と比べて賃料がどうしても低くなります。
アパート・マンションのように戸数の分だけ借主を増やせるわけではないため、収益性が劣ってしまうのです。
太陽光発電
敷地が広く、日光を遮るようなものが周囲にない更地では、太陽光発電の運営がオススメです。
太陽光パネルを設置し、発電した電力を電力会社に買い取ってもらうことができます。
事業用の太陽光発電(産業用太陽光発電)の買取価格は、経済産業省が「固定価格買取制度(FIT)」によって管理をしています。事業を開始した年から、20年間固定価格で買い取ってもらえるのです。
買取価格に関する詳細は以下のサイトを参考にしてください。(※2)
【メリット】
主なメリットとしては、
- 安定した収益を期待できる
- 初期費用の負担が大きくない
この2つです。
・安定した収益を期待できる
電力の買取価格は20年間固定価格であり、太陽光パネルの平均寿命はそれ以上の長さと言われています。よほどの気候変動が起きなければ、毎年安定した収益を期待できるでしょう。
・初期費用の負担が大きくない
賃貸アパート・マンション経営と比べると、初期費用の負担はそこまで大きくありません。
一般的には電力が10〜50kwの容量を採用するケースが多く、それくらいの容量であれば、数百万円〜1千万円台の予算でスタートできます。
さらに、太陽光発電の専門業者による一括借り上げ方式で運営するなら、初期投資ゼロで始めることも可能です。ただし、その際はただの「土地貸し」になってしまうため、収益性は下がります。
【デメリット】
主なデメリットとして、
- 天候に影響を受けやすい
- 節税効果がない
- 買取価格が年々安くなっている
この3つです。
・天候に影響を受けやすい
太陽光発電は、十分な太陽光がないと発電できないので、天候によって発電量が極端に下がることもあります。もちろん、夜間はほとんど発電できません。
・節税効果がない
建物を建てるわけではないため、固定資産税や都市計画税、相続税に関する節税効果は基本的にありません。
・買取価格が年々安くなっている
電力の買取価格が年々安くなっているのもデメリットです。2012年の時点では1kWh当たり40円でしたが、2020年では1kWh当たり13円まで買取価格が下がっています。
20年間価格が固定されること自体は、事業にとってリスクヘッジとなりますが、肝心の買取価格が安いと、低い利回りが20年間続くことになるのです。
買取価格が今後持ち直すかどうかは定かではないですが、参入のタイミングには慎重になった方がいいでしょう。
※2:「固定価格買取制度」(経済産業省)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/kakaku.html
土地売却
所有している更地に合いそうな活用方法がなければ、売却も視野に入れておきましょう。
相続した土地であれば、申告期限に近づくほど焦って売却することになるので、早めに専門の会社に相談することをオススメします。
【メリット】
主なメリットとしては、
- まとまった資金が手に入る
- 相続がスムーズ
この2つです。
・まとまった資金が手に入る
売却の一番のメリットは、現金資産が増えるということです。手に入れた資金を別の事業に再投資したり、債券や株式に変えたりなど、多くの選択があります。
・相続がスムーズ
労力という点でいえば、土地よりも現金の方が相続はスムーズです。複数人に土地を相続する場合、敷地内のどこからどこまでを誰に相続するか、不平等にならないよう慎重に決める必要があります。
その点、現金であれば基本的には配分を決めるだけでいいので、不要な論争やトラブルを避けやすいでしょう。
【デメリット】
主なデメリットとしては、
- 節税効果がなくなる
です。
・節税効果がなくなる
相続する手間を考えれば、土地より現金のほうが分割しやすいですが、相続税の負担は現金より土地のほうが軽くなります。
たとえば、1億円の資産があったとして、現金のまま相続すれば評価額はそのまま1億円です。
しかし、土地を相続しようとすると、評価額は1億円を下回るのが一般的です。
相続税の支払い額は、評価額によって変わりますから、税負担を少しでも軽減したいのであれば、売却せずに土地のまま相続することをオススメします。
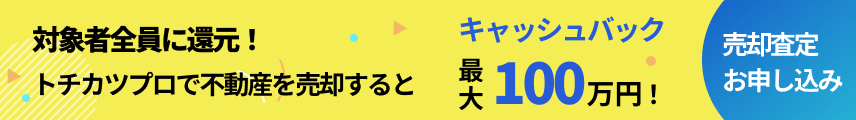
更地を土地活用する際に気をつけること

こちらでは、更地を活用する上での注意点について、
- 法律
- 条例
- 更地の測量
の3つを解説していきます。
建物を建てる前に、法律について最低限学んでおく
更地はさまざまな活用ができる可能性を秘めていますが、必ずしもオーナーの希望通りに活用できるとは限りません。
地域によって建設が許可されている建物の種類が決まっていたり、用途制限や設計上の制限がされていたりするからです。
少なくとも、都市計画法や建築基準法については触れておく必要があるでしょう。今回は、中でも重要な「用途地域」について解説します。
・用途地域
用途地域とは、1つの地域内で異なる用途が混在しないよう、都市計画法によって地域ごとに用途を定めた13種類のエリアのことです。詳しくは国土交通省のサイトを確認してみてください。(※3)
都市計画区域内にある土地は、それぞれ13地域のどこかに属しており、指定された用途に沿った建物しか建設が許可されていません。
例えば、「第一種低層住居専用地域」という地域では、アパート・マンション、賃貸住居の建設は許可されていますが、工場を建てることはできないのです。
「用途地域」は更地を活用する上でとても重要な知識です。建物の設計プランを立てる前に、必ず確認しましょう。他にも、建築基準法や借地借家法などにも触れておく必要があります。
実際には各自治体の建築指導課や都市整備部などを訪問し、検討中の活用方法が実現可能かどうか確認し、必要に応じて各法律を調べてみるといいでしょう。
※3「用途地域」(国土交通省)https://www.mlit.go.jp/common/000234474.pdf
地域の条例などを確認しておく
法律と合わせて押さえておきたいのが、「各地域の条例」です。
土地活用をおこなうには、法律に則った活用をするのはもちろん、自治体が独自に定めた条例も厳守する必要があります。
今回は、具体例として「奈良県景観条例」と「がけ条例」の2つを紹介します。
【奈良県景観条例】
こちらは、奈良県が独自に定めている条例です。地域の景観を守るため、既存の景観になじまないような色彩・建築物に対して、制限が設けられています。
実際に、条例が適用されるエリアでは、コンビニの看板や外壁が、定番カラーではなく黒や茶色に変更されていることがあるのです。また、建物の高さや形状が一律に揃っている地域などもあります。
ただし、条例が適用されるのは歴史的な建造物など、優れた景観を有する地域に限られます。もしも所有している更地がこのような地域に該当する場合、建築基準法をクリアしていても条例違反となるケースもあるので、注意が必要です。
【がけ条例】
がけ条例とは、敷地ががけに面していて(がけの上・下両方)、一定以上の高さである時、建物の建築に対して一定の制限をかけるというものです。
一般的には「2mまたは3mを超える、硬岩盤(こうがんばん)以外の土質で、30度以上の傾斜がある土地」が「がけ」として定義されています。
なお、がけ条例は全国各地で定められている条例であり、都道府県によって内容が異なります。
例えば、東京都のがけ条例(東京都建築安全条例第6条)では、高さ2m以上のがけに面した土地に建物を建てる際、がけの高さの2倍以上の距離を保って建てるか、2m以上の安全な擁壁を建てることが必要となっているのです。
所有している土地が「がけ地」か否かを確認するなら、自治体の建築指導課に相談するといいでしょう。自治体によってはインターネット上で情報開示しているケースもあるので、訪問前に該当のホームページを確認してみてください。
事前に更地の測量を済ませておく
更地の活用を検討しているのなら、まずは「測量」をオススメします。
測量とは、土地や隣地との境界線等について調査をし、測量図や資料を作成する作業です。土地家屋調査士に簡易的な測量を依頼することもできますが、できれば「境界確定測量」をおこないましょう。
境界確定測量とは、隣地の土地オーナーとが立会い、境界を確認する方法と、官公署の図面を用いて土地の境界を確定させる測量方法のことをいいます。
いまある更地を活用するにしても、売却するにしても、きちんと境界確定測量をしておいた方が後々スムーズに事が運びます。
たとえば、土地をテナントに貸し出す際、隣地所有者と境界トラブルが発生する可能性も減ります。また、境界の位置を双方で了解したものとして活用することができるため、借主側も安心して借りることができるのです。
売却の際も、買主から境界確定測量の調査資料を求められることがあり、事前に調査をおこなっておくと、契約がスムーズに進みやすいです。
参考までに、境界確定測量は以下のような手順で行われます。
⑴法務局調査
法務局によって、該当の土地やその隣地について、公図や地積測量図、全部事項証明書などの資料収集がおこなわれます。
⑵現況測量
土地家屋調査士が土地を測量し、測量図を作成します。
⑶道路境界確定
土地と隣接する道路について、境界が確定しているか調査がおこなわれます。確定できていない場合、官公署とともに境界を確定します。
⑷隣接地立会
法務局の作成した資料や測量図を用いて、隣地のオーナーの立会いのもと境界を確認します。
⑸筆界確認書作成
隣地のオーナーと境界の確認が済んだら、「境界標」という目印を土地上に設置します。
最後に、「筆界確認書」という資料を2通作成し、オーナーと隣地オーナーとで1通ずつ保管して、完了です。
なお、⑴〜⑸の全ての工程が完了するまでにかかる期間は3ヶ月前後で、費用はおよそ60万円〜80万円ほどかかります。
費用が少々高額な理由は、官公署の立会いがある場合、提出資料が多く、打ち合わせも頻繁におこなわれるため、労力も時間もかかってしまうためです。
境界確定測量は、時間がかかる上に費用も決して安くはありません。しかし、将来起こりうる隣地とのトラブルを防止することができますし、賃貸契約や売買契約を円滑に進めるためには、必要な下準備と言えます。
更地の土地活用なら近畿住宅流通へ
ここまで紹介してきたように、更地にはさまざまな活用の選択肢があります。
活用方法次第では初期投資ゼロで事業を始めることができますし、管理業務などを一切することなく毎月賃料を得ることも可能です。
しかし、それはあくまでも1つの例であり、必ずしもオーナーが選んだ活用方法で成功できるとは限りません。
実際には用途地域のような法的な制限や、各自治体ごとの条例などを遵守した上で、かつ、その土地の特性に合った活用プランを構築しなければならないのです。場合によっては、下手に土地を使って事業をするよりも、売却した方がいいというケースもあります。
いずれにしても、今更地を所有していて活用方法に悩んでいるという方は、近畿住宅流通にご相談ください。
30年以上にわたり、全国の土地を活用し続けてきた弊社だからこそ、伝えられる知識、経験、ノウハウがあります。ぜひ一度、お問い合わせください。
