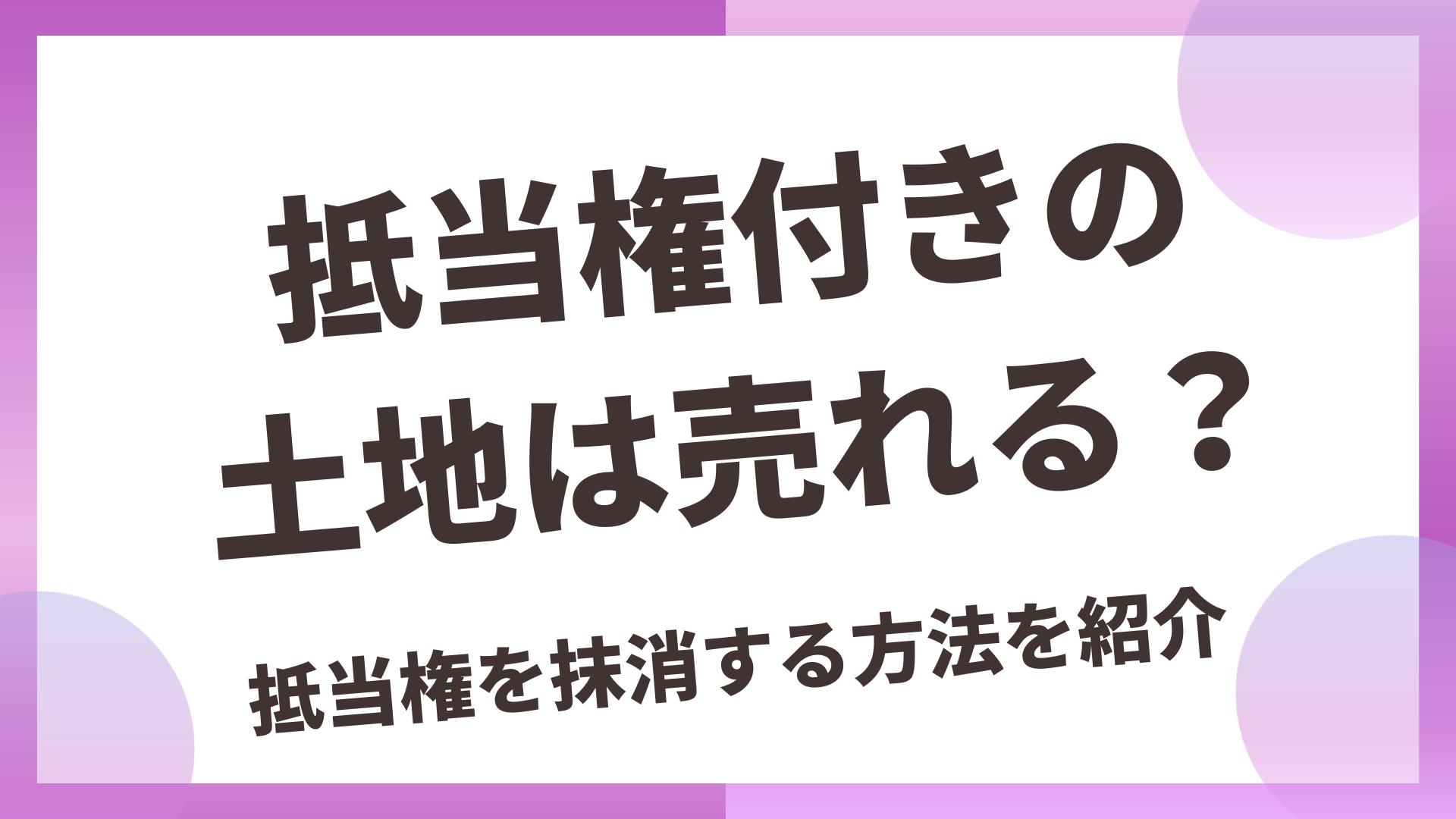不動産取引や相続時に頻繁に耳にする抵当権とは何なのか、また抵当権のついた土地は売却できるのか、抵当権に関する情報を網羅的に解説します。また、抵当権を抹消する方法やその費用も解説するので、参考にしてください。
抵当権のついた土地とは
そもそも抵当権とは何なのか、どうすれば抵当権を抹消できるのか、抹消にかかる費用相場はいくらか、順番に解説します。
抵当権とは
抵当権とは、住宅ローンを組む際に債権者(主に金融機関)が債務者に対して設定する権利です。ローン返済が契約通りにおこなわれなかった場合、債権者は債務者の土地や建物を担保にすることで不利益を軽減できます。たとえば、担保とする不動産を売却し、売却代金からローンを返済してもらうなどです。
抵当権を抹消するためには
抵当権つきの土地は売りにくいというリスクがあります。民法第379条によれば、抵当権つきの不動産を取得した第三取得者は、抵当権者に対して抹消請求が可能です。そこで、こちらでは抵当権を抹消する手順を紹介します。
⑴借金の全額返済
大前提として、借金を全額返済しないことには抵当権を抹消できません。ですので、担保となっている土地や建物に関連する借金を全額返済する必要があります。
⑵銀行から抹消に必要な書類をもらう
ローンの完済後、金融機関から抵当権解除証書、委任状、登記済権利証(または登記識別情報通知)などの書類が届きます。抵当権解除証書と委任状には記入欄があるので、すべて記入しましょう。記入ミスをすると再発行の手間が増えるので、注意してください。
なお、登記済権利証は原則として受け取り後の再発行ができません。法務局への抹消登記が完了するまで大切に保管しましょう。
⑶登記事項証明書を取得する
抹消の申請書等の書類に記入するために、不動産の情報が記載されている登記事項証明書を取得します。証明書は全国の法務局や法務出張所で取得可能です。また、登記事項証明書の取得には建物の家屋番号や土地の地番が必要となります。
なお、不動産所有者の現在の住所や氏名が登記事項証明書の内容と異なる場合は、抵当権を抹消する前に所有権登記名義人表示変更登記が必要です。
住所が変更されている場合は住民票か戸籍の附票、氏名が変更されている場合は戸籍謄本を持参して、変更手続きをおこないましょう。
⑷法務局に抵当権抹消の登記申請書を出す
必要書類が揃ったら、管轄の法務局へ登記申請書を出します。申請書の提出は窓口と郵送のどちらでも可能です。なお、登記申請書の見本は以下となります。
⑸法務局で登記完了の書類を受け取る
申請した内容に問題がなければ、その場で伝えられる登記完了予定日通りに登記が完了するので、書類を取りに行きましょう。
抵当権の抹消手続きに必要な書類
抵当権の抹消手続きに必要な主な書類は、以下の通りです。
- 抵当権抹消登記申請書
こちらは抵当権抹消を法務局に申請するためのものです。法務局のホームページからダウンロードできます(※1)。
- 登記識別情報または登記済証
抵当権を設定した際に、抵当権者に渡される書類です。住宅ローンを完済後、該当する金融機関から送付されるのが一般的です。
- 登記原因証明情報
こちらは、抵当権解除証書や返済完了の証明書などが該当します。住宅ローンの完済後、金融機関から提供されるのが一般的です。
- 抵当権者の委任状
抵当権抹消の際の登記は、土地や家の所有者と抵当権者の双方で共同でおこなうのが一般的です。金融機関が発行する委任状があれば、登記が可能となります。
抵当権の抹消にかかる費用
こちらでは抵当権の抹消の際に発生する費用を紹介します。
- 登録免許税
不動産の所有権を変更したり、抵当権の設定・抹消登記の際に法務局に収める税金です。こちらは不動産1つの抹消につき1000円となります。
- 司法書士報酬
抵当権の抹消手続き全般を司法書士に依頼する場合、別途報酬の支払いが必要です。なお、相場は1万5千円前後となります。
- 事前調査費用
抵当権抹消の手続きをする前に、不動産の所在や面積などの登記内容を調べる際にかかる費用です。1つの不動産につき335円がかかります。全部事項証明書や登記事項要約書を取得する場合は、それぞれ600円(オンラインでの取得は500円)、450円の費用が発生します。
抵当権のついた土地は売却できるのか

多くの人が抵当権のついた土地や建物は売却できないと誤解していますが、そんなことはありません。そこでこちらでは抵当権つきの土地の売却事情について解説します。
抵当権がついていても売却可能
繰り返しになりますが、抵当権がついた土地や建物だとしても、売却は可能です。売却を禁止する法律もないので、罰されることもありません。ただし、一般的には抵当権の抹消後に売却するか、売却と同じタイミングで抹消します。なぜなら、抵当権つきの土地や建物の購入は、買主にとって大きなリスクを伴うからです。
たとえば、購入後に売主が抵当権を外せなかった場合、その土地や建物はいつ競売にかけられるかわからない状態が続きます。さらに、抵当権つきの物件に融資をする金融機関はまずいないので、ある程度の資本力がある買主を見つけられないと、売却は難しいでしょう。
売却で得た資金で借金返済も可能
売却で得た資金を借金返済に充てて、抵当権を抹消する人も多いです。たとえばマンションを売却するのであれば、売却益をそのまま住宅ローンの返済に充てる(同時決済)などです。ローン返済後に金融機関に申請を出し、抵当権が抹消されたら、不動産の名義を買主に変更します。
抵当権のついた土地は『任意売却』ができる
借金の返済が困難になった場合や、資金繰りに困った場合に、抵当権がついた土地や建物の売却を考える人は少なくありません。しかし、先述のように抵当権つきの土地や建物は中々簡単には売れません。最終的には強制的に「競売」にかけられて、強制的に割安で買い叩かれるのが落ちです。
しかも、競売では手数料がかかる上に、売却益から捻出することができません。あくまで自分で手数料を捻出する必要があります。そこで、抵当権つきの土地や建物が売れなかったときの、競売以外の売却方法の1つが「任意売却」です。
任意売却とは、売却後も借金返済が残ることについて、金融機関の合意を得てから売却する方法です。任意売却であれば、相場に近い価格帯で売却できます。
一度競売にかけられると、あとで任意売却に変更することは難しいので、返済の目処が立たない場合はできるだけ早めに金融機関に相談することをオススメします。
そもそも抵当権つきの土地は相続しない方がいいのか?
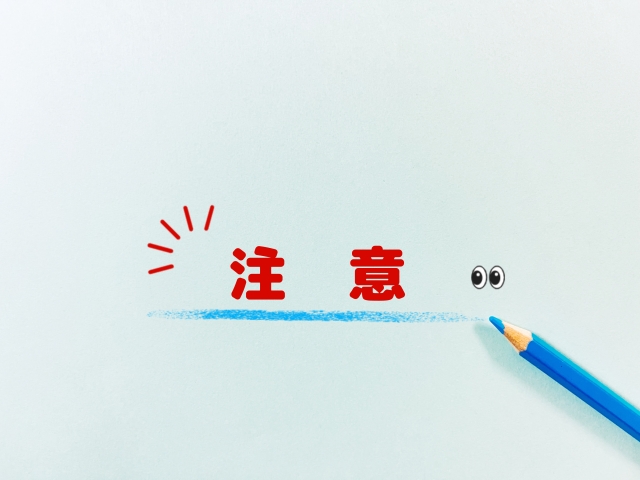
抵当権つきの土地の売却が難しいことはここまで解説した通りです。では、そもそも抵当権つきの土地は相続しない方がいいのでしょうか。そこで、こちらでは抵当権つきの土地を相続することの是非、また相続したくないときの対処法を解説します。
基本的にはデメリットが多い
抵当権つきの土地は、いわばマイナスの資産です。相続と同時に借金返済の義務も背負うことになるので、土地の規模によっては大きな金銭的負担がのしかかります。
さらに、抵当権つきの土地だとしても、相続する際は相続税が発生します。抵当権がついていても土地の評価には影響がないので、きちんと課税対象になるのです。そのため、抵当権つきの土地の相続は、基本的にデメリットが多いと言えるでしょう。
借金が返済できないなら相続放棄も可能
土地を相続するメリットがなかったり、借金返済の目処が立たなかったりする場合は、相続放棄をオススメします。相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内であれば申請が可能です。
ただし、相続放棄をしたからといってそれで借金から完全に解放されるわけではありません。仮に相続人全員が相続放棄をしたとしても、清算が完了するまでは誰かが財産を管理する必要があります。
そこで、財産の管理を任されるのが「相続財産管理人」です。一般的には家庭裁判所によって弁護士が選任され、申し立てをしてから選任が決まるまでは1〜2ヶ月ほどかかります。
なお、相続財産管理人への依頼は無料でできるわけではありません。費用は財産の規模や内容によって変わりますが、10万円〜100万円程度の予納金、月1万円〜5万円程度の費用がかかります。
相続人全員が相続放棄し、他の財産からの回収も見込めない場合の借金は、基本的に連帯保証人に請求がいきます。そのため、相続人兼連帯保証人の方は、仮に相続放棄をしても連帯保証債務は有効ですので注意が必要です。
土地売却における抵当権に関連してよくある質問
抵当権と担保は何が違うのですか?
担保の方法は2つあり、そのうちの1つが「抵当」になります。意味は、債権者が担保となる対象物を占有することです。抵当において、債権者は対象物を使用して収益化することが認められています。
そのような抵当の権利が契約や登記で規定されていることを抵当権と言います。なお、担保のもう1つの方法は「質」です。質は、債権者が対象物そのものを占有することを指します。
抵当権者と抵当権設定者の違いは何ですか?
抵当権者とは、担保として抵当権をつけた者(金融機関など)のことです。また、抵当権設定者とは、担保として所有する不動産を差し出した者を指します。
抵当権の有無は相続税の土地評価に影響しますか?
抵当権の有無自体は、土地の相続税評価に直接の影響を与えません。しかし、土地の評価はその時点の市場価格に基づくため、抵当権が存在することで市場価格が低下する可能性がある場合、間接的に影響を受けることもあります。
土地売却のご相談は近畿住宅流通へ
そもそも土地売却をスムーズに進めるには、多くの法的手続きをこなす必要があります。抵当権がついた土地を売る場合、その複雑さは一層増します。本記事でもお伝えした通り、抵当権を抹消する際は司法書士などの協力を得て、適切に手続きを進めてください。
なお、近畿住宅流通では北海道から沖縄まで、全国で土地の買取を積極的におこなっています。抵当権の抹消が終わっていない土地の売却に関しても、お気軽に弊社までご相談ください。